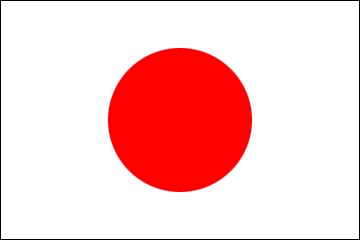代表部の仕事:貿易と環境持続可能性 ~WTO有志国イニシアティブの現在地~
令和6年6月12日
貿易と環境持続可能性
~WTO有志国イニシアティブの現在地~
~WTO有志国イニシアティブの現在地~
森井 一成 参事官
1 はじめに
私は2022年春から2年以上にわたり、WTO(世界貿易機関)の貿易と環境持続可能性に関する有志国イニシアティブであるTESSD(Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions:貿易と環境持続可能性に関する体系的議論)[1]の循環経済WG(ワーキンググループ)の共同ファシリテーターを務めてきました。今回はその仕事のご紹介を通じて、WTOが今日のグローバル・アジェンダと貿易の関連についての作業を模索する過程をお伝えしたいと思います。
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)
2 TESSD立ち上げとファシリテーター就任
WTOにおけるマルチ(多国間)のルール交渉が困難になり、プルリ(有志国間)でルール形成を目指す試みが行われていることは、これまでも紹介されてきました(グローバルなデジタル経済の発展に向けて~WTO電子商取引交渉の取組~/サービス貿易に影響を与える国内規制に関する国際的ルール形成/WTOにおける投資円滑化交渉)。本稿で取り上げるTESSDは、同じくプルリの取組ではありますが、交渉開始を前提としない探求的な議論の枠組みである点にその特徴があります。
環境持続可能性に関する国際的な議論が高まる中で、2020年11月、日本を含む50加盟国が、WTOで貿易と環境持続可能性の関連について議論を深めていく意思を示す共同コミュニケ[2]を発出しました。これに基づき、カナダとコスタリカが共同開催国となってTESSDが立ち上げられます。約1年の全体的な議論を経て、21年12月にはより具体的な作業の方向性に合意した有志国閣僚声明[3]が採択されました。22年に入って、テーマ別に作業を行うための4つのWG(環境物品サービス、貿易関連気候措置、循環経済、補助金)が設置されることになり、私はチリとともに循環経済WGの共同ファシリテーターに選ばれたのでした。

【TESSD循環経済WG会合の様子】
3 循環経済WGファシリテーターとして
就任当初、私はWGの作業をどのように進めるべきかやや逡巡していました。伝統的なWTOの交渉議長とは明らかに異なる役割だったからです。交渉であれば、妥結という最終目標に向けて、各国からの具体的な交渉の方法や内容の提案を踏まえ、調整を行い、道筋を付けていくという役割は比較的分かりやすいものです。しかし、TESSDは交渉を前提とはせず、「環境持続可能な貿易の機会を拡大するための具体的な行動を特定する」という抽象的な作業目標を設定されていました。また、WGのテーマである循環経済について各国と非公式に議論を重ねる中で分かったことは、多くの国が循環経済に関連する政策を立案・実施しつつあるものの、それらは基本的に国内政策(典型的には国内の家電リサイクルなど)であって、貿易と循環経済の関連性について、加盟国間に必ずしも共通認識はないということでした。
そこで、私はもうひとりのファシリテーターやWTO事務局と、WG作業の基本的な考え方について話しました。それは、まずは「何が循環経済の貿易関連課題なのか」について加盟国間の共通認識をつくる必要があるということです。そして、そのためには実際に循環経済への移行のために活動している企業や団体が、具体的に何に困っているのか、それをどう乗り越えようとしているのかを共有する必要があるということです。我々はこの基本的な考え方に従い、年4回程度のWG会合について、毎回加盟国が関心を持つ産業分野や課題を聴取し、論点(ガイディング・クエスチョン)を設定し、知見のある企業・団体の専門家などにプレゼンテーションを依頼し、WG会合の進行を担ってきました。
我々が行ってきた議論を簡潔にまとめるとこのようになります。これまでの私達の経済活動の大半は、新たな資源を採掘・生産して製品を作り、使用し、廃棄するという「単線型」モデルでした。これに対して循環経済とは、既に使われている資源をなるべく経済活動のループの中に残し、資源の新規投入と廃棄を最小化する「循環型」の生産・消費モデルを指します。ここで重要なことは、製品のライフサイクル全体を視野に入れ、使用後のリサイクルなど個別の取組に留まらず、設計・生産段階から資源を何度も活用するためのデザインやビジネスモデルを考える必要があるということです。
では、循環経済と貿易はどのようにつながるのでしょうか?例えばある国の企業が、各生産段階でリサイクルに役立つ原材料情報を製品に付帯する取組を進めたとしても、他国のリサイクル施設で活用していない形の情報では意味がなくなってしまいます。そうした付帯情報や関連基準を国際的に調和することで、循環経済に資する貿易を円滑化できるかも知れません。また、ある企業が、複数国で販売・使用されている製品をA国の施設に集約してリサイクルすることが効率的と考えた場合、各国で回収された使用済製品をA国に輸入する必要があります。しかし、A国の税関当局には、それが国内で適切にリサイクルされるのか知るすべはなく、使用済製品を「廃棄物」と分類し、不法投棄防止等の目的で輸入制限しているかも知れません。そこで、用途を含む分類・基準の策定を促したり、リサイクル施設や事業者の認証スキームを作ったりすることは、助けになるかも知れません。
様々な外部専門家からのインプットを得ながら行ってきたこのような議論は、実際に起きている具体的な貿易関連課題に焦点を当て、環境持続可能性に関する政治的な立場の違いを超えて、加盟国間で共通認識を形成するという観点で有効なものだったと思います。そして、約2年間のWG作業の成果は、24年2月に開催されたMC13(第13回WTO閣僚会合)の機会に、循環経済の貿易関連課題をまとめたマッピング文書[4]として取りまとめることが出来ました。

【WTO Public Forum 2023 貿易と循環経済関連セッションの様子】
4 貿易と環境持続可能性、そして有志国イニシアティブの現在地
TESSDに77加盟国(24年5月時点)が参加していることは、WTOにおいて、環境持続可能性というグローバル・アジェンダに対する貿易の役割について議論する必要性を、多くの国が共有していることを示しています。同時に、そこにはいくつかの挑戦もあると感じています。まず、環境持続可能性の「貿易関連課題」について、どのように議論し、WTOでの具体的成果にできるのかについて、まだ探求段階にあるということです。WTOは、前身のGATT時代から、貿易自由化とそれを支える公正な貿易ルールの形成を主目的としてきました。環境の保護・保全という価値もWTOを設立するマラケシュ協定(1995年発効)の前文に明記されていますが、WTOでの議論は基本的に、環境目的に資する環境物品などの「自由化交渉」を目指すか、WTO協定と多国間環境条約等との外縁的な「調整問題」として検討するか、いずれかだったように思います。
背景には、各国内においても、貿易政策と環境政策その他の関連政策が夫々の政策コミュニティの中で立案・実施されてきた結果、各コミュニティを横断的に巻き込んだ国際的議論があまり行われてこなかったという状況もあるように思います。とりわけ貿易当局の間では、環境持続可能性という従来の主目的の外にある目標にどのようにアプローチすべきかについて、共通認識は出来ていないように見えます。TESSDの探求的な作業は、こうした問題意識から、外部専門家や環境関連の国際機関等との交流を増やし、彼らの知見を学ぶところから作業を始める試みとも言えるでしょう。
同時に、この探求的議論が目指すべき具体的成果についても、共通認識は得られていません。貿易自由化やルール形成は、貿易政策のステークホルダーにとって分かりやすい成果であり、今後、環境持続可能性にも資するそのような交渉が立ち上がる可能性もあるでしょう。同時に、例えば上述のような循環経済と貿易の諸課題に対処するには、交渉というよりはガイドラインやベストプラクティス、国際的な協調行動の推進などのような幅広いアプローチを検討する必要があるかも知れません。
TESSDは、WTOの有志国イニシアティブという枠組みが、現代のグローバル・アジェンダについて実務的・具体的に作業を開始するために有益な枠組みになり得ることを示してきたと思います。そして、私のファシリテーターとしての仕事は、そうした有志国イニシアティブの作業を、どのように具体的成果につなげられるかという試行錯誤のプロセスでもありました。WTOがこれまでとは異なる新たな付加価値を生み出せるのか、その命題に向き合いながら歩みを進めていきたいと考えています。
私は2022年春から2年以上にわたり、WTO(世界貿易機関)の貿易と環境持続可能性に関する有志国イニシアティブであるTESSD(Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions:貿易と環境持続可能性に関する体系的議論)[1]の循環経済WG(ワーキンググループ)の共同ファシリテーターを務めてきました。今回はその仕事のご紹介を通じて、WTOが今日のグローバル・アジェンダと貿易の関連についての作業を模索する過程をお伝えしたいと思います。
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)
2 TESSD立ち上げとファシリテーター就任
WTOにおけるマルチ(多国間)のルール交渉が困難になり、プルリ(有志国間)でルール形成を目指す試みが行われていることは、これまでも紹介されてきました(グローバルなデジタル経済の発展に向けて~WTO電子商取引交渉の取組~/サービス貿易に影響を与える国内規制に関する国際的ルール形成/WTOにおける投資円滑化交渉)。本稿で取り上げるTESSDは、同じくプルリの取組ではありますが、交渉開始を前提としない探求的な議論の枠組みである点にその特徴があります。
環境持続可能性に関する国際的な議論が高まる中で、2020年11月、日本を含む50加盟国が、WTOで貿易と環境持続可能性の関連について議論を深めていく意思を示す共同コミュニケ[2]を発出しました。これに基づき、カナダとコスタリカが共同開催国となってTESSDが立ち上げられます。約1年の全体的な議論を経て、21年12月にはより具体的な作業の方向性に合意した有志国閣僚声明[3]が採択されました。22年に入って、テーマ別に作業を行うための4つのWG(環境物品サービス、貿易関連気候措置、循環経済、補助金)が設置されることになり、私はチリとともに循環経済WGの共同ファシリテーターに選ばれたのでした。

【TESSD循環経済WG会合の様子】
3 循環経済WGファシリテーターとして
就任当初、私はWGの作業をどのように進めるべきかやや逡巡していました。伝統的なWTOの交渉議長とは明らかに異なる役割だったからです。交渉であれば、妥結という最終目標に向けて、各国からの具体的な交渉の方法や内容の提案を踏まえ、調整を行い、道筋を付けていくという役割は比較的分かりやすいものです。しかし、TESSDは交渉を前提とはせず、「環境持続可能な貿易の機会を拡大するための具体的な行動を特定する」という抽象的な作業目標を設定されていました。また、WGのテーマである循環経済について各国と非公式に議論を重ねる中で分かったことは、多くの国が循環経済に関連する政策を立案・実施しつつあるものの、それらは基本的に国内政策(典型的には国内の家電リサイクルなど)であって、貿易と循環経済の関連性について、加盟国間に必ずしも共通認識はないということでした。
そこで、私はもうひとりのファシリテーターやWTO事務局と、WG作業の基本的な考え方について話しました。それは、まずは「何が循環経済の貿易関連課題なのか」について加盟国間の共通認識をつくる必要があるということです。そして、そのためには実際に循環経済への移行のために活動している企業や団体が、具体的に何に困っているのか、それをどう乗り越えようとしているのかを共有する必要があるということです。我々はこの基本的な考え方に従い、年4回程度のWG会合について、毎回加盟国が関心を持つ産業分野や課題を聴取し、論点(ガイディング・クエスチョン)を設定し、知見のある企業・団体の専門家などにプレゼンテーションを依頼し、WG会合の進行を担ってきました。
我々が行ってきた議論を簡潔にまとめるとこのようになります。これまでの私達の経済活動の大半は、新たな資源を採掘・生産して製品を作り、使用し、廃棄するという「単線型」モデルでした。これに対して循環経済とは、既に使われている資源をなるべく経済活動のループの中に残し、資源の新規投入と廃棄を最小化する「循環型」の生産・消費モデルを指します。ここで重要なことは、製品のライフサイクル全体を視野に入れ、使用後のリサイクルなど個別の取組に留まらず、設計・生産段階から資源を何度も活用するためのデザインやビジネスモデルを考える必要があるということです。
では、循環経済と貿易はどのようにつながるのでしょうか?例えばある国の企業が、各生産段階でリサイクルに役立つ原材料情報を製品に付帯する取組を進めたとしても、他国のリサイクル施設で活用していない形の情報では意味がなくなってしまいます。そうした付帯情報や関連基準を国際的に調和することで、循環経済に資する貿易を円滑化できるかも知れません。また、ある企業が、複数国で販売・使用されている製品をA国の施設に集約してリサイクルすることが効率的と考えた場合、各国で回収された使用済製品をA国に輸入する必要があります。しかし、A国の税関当局には、それが国内で適切にリサイクルされるのか知るすべはなく、使用済製品を「廃棄物」と分類し、不法投棄防止等の目的で輸入制限しているかも知れません。そこで、用途を含む分類・基準の策定を促したり、リサイクル施設や事業者の認証スキームを作ったりすることは、助けになるかも知れません。
様々な外部専門家からのインプットを得ながら行ってきたこのような議論は、実際に起きている具体的な貿易関連課題に焦点を当て、環境持続可能性に関する政治的な立場の違いを超えて、加盟国間で共通認識を形成するという観点で有効なものだったと思います。そして、約2年間のWG作業の成果は、24年2月に開催されたMC13(第13回WTO閣僚会合)の機会に、循環経済の貿易関連課題をまとめたマッピング文書[4]として取りまとめることが出来ました。

【WTO Public Forum 2023 貿易と循環経済関連セッションの様子】
TESSDに77加盟国(24年5月時点)が参加していることは、WTOにおいて、環境持続可能性というグローバル・アジェンダに対する貿易の役割について議論する必要性を、多くの国が共有していることを示しています。同時に、そこにはいくつかの挑戦もあると感じています。まず、環境持続可能性の「貿易関連課題」について、どのように議論し、WTOでの具体的成果にできるのかについて、まだ探求段階にあるということです。WTOは、前身のGATT時代から、貿易自由化とそれを支える公正な貿易ルールの形成を主目的としてきました。環境の保護・保全という価値もWTOを設立するマラケシュ協定(1995年発効)の前文に明記されていますが、WTOでの議論は基本的に、環境目的に資する環境物品などの「自由化交渉」を目指すか、WTO協定と多国間環境条約等との外縁的な「調整問題」として検討するか、いずれかだったように思います。
背景には、各国内においても、貿易政策と環境政策その他の関連政策が夫々の政策コミュニティの中で立案・実施されてきた結果、各コミュニティを横断的に巻き込んだ国際的議論があまり行われてこなかったという状況もあるように思います。とりわけ貿易当局の間では、環境持続可能性という従来の主目的の外にある目標にどのようにアプローチすべきかについて、共通認識は出来ていないように見えます。TESSDの探求的な作業は、こうした問題意識から、外部専門家や環境関連の国際機関等との交流を増やし、彼らの知見を学ぶところから作業を始める試みとも言えるでしょう。
同時に、この探求的議論が目指すべき具体的成果についても、共通認識は得られていません。貿易自由化やルール形成は、貿易政策のステークホルダーにとって分かりやすい成果であり、今後、環境持続可能性にも資するそのような交渉が立ち上がる可能性もあるでしょう。同時に、例えば上述のような循環経済と貿易の諸課題に対処するには、交渉というよりはガイドラインやベストプラクティス、国際的な協調行動の推進などのような幅広いアプローチを検討する必要があるかも知れません。
TESSDは、WTOの有志国イニシアティブという枠組みが、現代のグローバル・アジェンダについて実務的・具体的に作業を開始するために有益な枠組みになり得ることを示してきたと思います。そして、私のファシリテーターとしての仕事は、そうした有志国イニシアティブの作業を、どのように具体的成果につなげられるかという試行錯誤のプロセスでもありました。WTOがこれまでとは異なる新たな付加価値を生み出せるのか、その命題に向き合いながら歩みを進めていきたいと考えています。
[1] https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/tessd_e.htm
[2] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/CTE/W249.pdf&Open=True
[3] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/6R2.pdf&Open=True
[4] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN24/11A4.pdf&Open=True