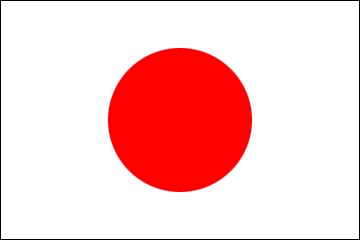代表部の仕事:国際ルール交渉かくありき -知的財産関連の三者三様の交渉現場から-
令和6年8月2日
国際ルール交渉かくありき
-知的財産関連の三者三様の交渉現場から-
-知的財産関連の三者三様の交渉現場から-
安居 拓哉 一等書記官
1.はじめに
ジュネーブでは国際機関においてほぼ毎日のように多数国間での議論が行われています。それは予算や各種プロジェクトに関するものであったり国際ルールの交渉であったり多種多様。中でも条約・協定といった国際ルールに関する交渉となると、各加盟国の法制度・実務や実体経済等に直接影響を及ぼすため、各国交渉団の熱量は生半可なものではありません。では、そのような交渉の経験が長年蓄積してきたジュネーブには、交渉を円滑に進めるための最適な手法というものは確立しているのでしょうか。
私は2021年秋に在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に赴任して以来、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)、さらには世界保健機関(WHO)において知的財産関連のルール交渉の場に参加する機会を得ました。その中で見いだせた上記問いに対する答えは、国際機関ごとに交渉の進め方は全く異なり統一的な交渉の進め方など存在しない、ということでした。各機関の所掌範囲や交渉目的等が異なるという側面は当然ありますが、今回は、知的財産ルール交渉への参加経験という狭い視点からとはいえ、ジュネーブにおけるWTO、WIPOそしてWHOでのルール交渉の現場について、簡単にご紹介できればと思います。
なお、本稿は特にWTOでのCOVID-19知財ウェイバー交渉、WIPOでの遺伝資源関連条約交渉、WHOでのパンデミック条約交渉への参加経験(2022~24年)に基づくものであり、ジュネーブの交渉全てに一般化できるものではない点ご容赦ください。それぞれの実体的交渉内容や日本としての考え方については、その紹介だけで長大になってしまうので、今回は紙面の都合上割愛します。
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)

(ジュネーブの国際機関が集まる地区にそびえるWIPO本部ビル)
2.真の交渉は大会議場の公式会合では起きていない
国際機関において最終的に条約や協定といった国際ルールに合意するには、当然ながらそれなりの会議場での公式会合といった正式な決定の場が必要です。ただ、その合意に至るための交渉も公式会合だけで済むのかといえば、全くそのようなことはありません。百数十もの国が加盟する国際機関において、公式な会合の場だけで議論が収束する可能性など極めて稀です。この点については、WTO/WIPO/WHOいずれの国際機関も共通しています。
交渉会期中に実際に交渉を進めるために何が重要かといえば、公式会合の合間等に実施される非公式会合であり、その形態は多種多様です。議論メンバーは変えず会合の名前だけ「非公式会合」としたものもあれば、議長が特定メンバーだけ招集する少数国会合、関心国同士での自発的な二国間協議などなど。このような非公式会合は、発言が記録に残らないこともあり、各国が率直に妥協点を探るための膝詰めでの交渉を可能にするのです。もちろん、交渉の前に、同志国同士の準備会合を行い戦略を練ったり、自国の味方を増やすための根回し会合を実施しておくことも不可欠です。
では、最終的な議論終結の機会以外に、公式会合とは一体どのような意味を持つのでしょうか。これも国際機関によって様々ですが、交渉団以外の者の傍聴も認められたり、その場での発言が正式なものとして受け取られるといった点で非公式会合と異なり得ます。特に後者に関しては、公式会合での発言が交渉記録として正式な議事録に残されるという場合があります。各国の交渉団はその国を代表して参加しているのであり、それぞれには各国の立場というものがあります。その立場を表明し議事録に記すことにより、自らの国がどのような立場で交渉に臨んでいるかを対外的に示すことができるのです。デメリットとして、そのために公式会合では政治的ポジションを記録に残すための言いっ放しの場にもなりがちで、何ら歩み寄りが見られない冗長な時間に感じられる部分は確かにあるのですが、一方で、後世においても発言が参照できるという点は重要です。一例として、交渉において条約・協定の文言についてせめぎ合いがある場合、双方が受け入れられるように敢えて解釈の余地を残す「建設的曖昧さ(constructive ambiguity)」という形で決着が図られることがあります。このとき、公式会合において「自国としてはこのように解釈している」といった形で発言し記録に残すことで、後々に解釈について争いとならぬよう根拠を残しておくという使い方もできるのです。

(WHOパンデミック交渉で発言する筆者)
3.関心国だけでの交渉と透明性との両立
上述のように、互いに妥協点を探る真の交渉を進める上では非公式会合の存在はほぼ必須となりますが、いつから、どの国を集めて、どこでそのような会合を行うのか、という点が問題となります。最初から少数国だけ集めようにも、誰がキープレイヤーか・何に関心があるかは全く分かりませんし、そのために交渉参加国全体の意見を聴き全体的な温度感や落としどころを見定めることは交渉成功のために重要であるとはいえ、いつまでも同じ政治的ポジションの発言を繰り返す国もあります。そのような中で単に「非公式会合」とだけ名前を変えて全員で議論をするだけでは、議論が進んでいきません。そのため、適切な段階で交渉論点のキープレイヤーとなる国を集め、真の着地点を見極めるための少数国調整を行うことが、交渉成功への鍵となります。
この少数国会合に関連し特に有名なのが、WTOの「グリーンルーム」と呼ばれる会合です。WTOウェブサイトの用語集にも掲載されていますが、これは事務局長の会議室に由来するもので、特に各国の交渉代表団トップのみ(状況によりプラス随行者1名)20~40名程度が参加できる会議です。交渉においてある程度論点が絞られ、そのキープレイヤーがぼんやりと特定できたあたりから、事務局長がグリーンルーム会合を招集して一気に議論の加速化や収束を図ることがあります。なお、グリーンルームの名前は、過去に事務局長会議室の壁等が本当に緑だったことに由来するようですが、今は緑ではないようです。また、WTO以外の場所で閣僚会議が開催される場合であっても、同様のハイレベル少数国会合がグリーンルーム会合と呼ばれるようになっています。
さらに際立った例として、WTOのCOVID-19ワクチン等に関する知財ウェイバー交渉時の進め方があります。この交渉においては、議論が尽くされ膠着状態に陥った際、交渉における極めて重要なプレイヤーと考えられた数か国に対し事務局長等が働きかけ、そのメンバー間のみで最初の合意テキスト案を検討させました。その結果ドラフトされたテキスト案が、その後少数国会議や全体会合に提示され、徐々に交渉メンバーの範囲を拡張するという手法を経て、最終的には閣僚決定として合意に至ることになりました。各国の立場が極めて離れていた本交渉の中で、交渉のキープレイヤーの中で率直に議論する場を作り、まずは核となる要素だけでも合意を得てしまう(要は、関心国だけで「握る」)ことが、確実な交渉成果に至る上で重要だったといえます。
もちろん、少数国会合には問題点もあります。特定の国だけで交渉を進めようとすると、蚊帳の外に置かれた国々は強い不満を抱きます。実際にWTOでの上記進め方は、透明性が欠如していると多くの国から批判を受けることにもなりました。これに対し対照的だったのがWHOパンデミック条約交渉です。この条約交渉はまだ継続中ではありますが、非公式会合という形であったとしても多くの交渉が交渉団全体で行われ、これまでのところWTOのグリーンルーム会合といったハイレベル少数国交渉はあまり聞くことがありません。これは、本条約が今後のパンデミックに対する予防・備え・対応を強化するためのもので、だからこそ知財に限らない広範な論点が多く、キープレイヤーが特定しにくいという課題もあったからかもしれません。とはいえ、キープレイヤーのみでの集中的議論の機会がない分、交渉は進みづらいともいえます。
こういったWTOやWHOでの交渉を横目に見ていたのか、WIPOの遺伝資源関連条約交渉はまさにその中道を通り、少数国会合と透明性の両立に腐心していました。同交渉では、まず議長は全体会合の場で交渉参加国に一通り発言させ、各交渉団の関心点やその度合いを見定めました。そして、そのままでは交渉局面が動かないと見るや、中規模会議室に非公式会合の場を移し、まずは各国からの物理的参加人数を制限。それでも参加国数が変わらず状況が打破できないと判断し、最終的には、メインテーブルに30~40名程度座れる小規模会議室を交渉部屋としました。これにより、発言できる物理的人数や国数が絞られ、率直な議論の空間を確保しました。一方、WTOのグリーンルーム等とは異なり、議長はキープレイヤーを指名することはせず、各地域グループ(WIPOには7つの地域グループがあります)にメインテーブル座席数を割り当てるに留めます。そして、誰が座り発言するかは地域グループ内で決定するよう判断を委ねて、議長としての中立性を徹底。加えて、発言者は同じ地域グループ内の国同士でローテーションし譲り合ってもよい仕組みとすることで、関心があるのに発言できないという不満を解消。さらにその交渉部屋の会合の様子は全体会合用の議場に投影し全員が傍聴できる仕組みとすることで、透明性の課題も克服されました。結果として、条約の交渉は無事にまとまった一方で、透明性についても各国から不平不満を聞かないという、バランスの取れた形で交渉が進められたように見えました。

(WIPOの大会議場)

(交渉終盤のWIPO小規模会議室)
4.交渉テキストはどこからやってくるのか
最終的に条約・協定・決議・決定といったいずれの形を目指すにせよ、国際ルールに関する交渉であればベースとなるテキストがあり、それに基づいて交渉が行われます。では、交渉のベースとなるテキストは誰が用意するのでしょうか。
WTOの知財ウェイバー交渉では、当初、特定の国々からCOVID-19ワクチン等の知的財産保護義務の免除(=ワクチン等を知的財産で保護しない)の提案が出されました。しかしながら、この提案には当然ながら反対国も多く、これ自体では実体的なテキスト交渉が始まることすらありませんでした。提案内容に関し集中的議論は行ったものの、具体的な交渉ベースがなければ結局は空中戦のようなもので、案の定議論は膠着状態。そのような中、3.で触れたように状況を打開すべく事務局長が動き、交渉のキープレイヤー数か国に働きかけ対話を促した結果、その中で練られた結果が交渉テキストのベースとなったのです。このように、WTOの場合、キープレイヤーの間である程度合意できるような素地を先に作るという形で、交渉が進められたといえます。
WHOのパンデミック条約交渉の場合には、まずどのような要素がパンデミック対応のために必要なのか、という点から各国間で議論をスタートする必要がありました。様々な要素が含まれ得るためキープレイヤーの特定などほぼ不可能。そのため、議論の進行役であるビューローとWHO事務局は、加盟国へのアンケート等を通じて、まず「コンセプチュアル・ゼロドラフト」として条約のコンセプトを提示。これに対し出された意見を踏まえ、次に「ゼロドラフト」が公開されました。ここまでは、加盟国からの要望をすべて詰め込んだものという性質のテキストです。その後、更なる議論を経て複数のオプションへと整理された「ビューロー・テキスト」、それらへの意見を踏まえ中立的なものへ収斂させた「ネゴシエーション・テキスト」と、議論を経るたび出世魚のようにそのテキストの名前は次々に変化していきました。一方で、その内容も徐々に条約といえるような形へと進化。このいずれのテキストも、特定国ではなくビューロー・事務局側から提示されたものでしたが、これは、WHOでは条約のカバー範囲が広い上に交渉参加国のニーズだけに基づく各国提案自体では懸隔が大きすぎるため、議論全体の温度感を踏まえてビューロー・事務局が折衷案を作らざるを得なかったためといえます。
WIPOの遺伝資源関連条約交渉で交渉テキストとなったのは、関連委員会での議長(当時)が数年前に個人として提案した「議長テキスト」と呼ばれるものでした。これを交渉テキストとするか否かについても一悶着あったものの、この関連委員会では、議長テキスト提案に至るまでに20年強という長年の議論の蓄積がありました。さすが20年以上の議論を経ているだけあり、この議長テキストは加盟国全体の要望バランスを取ろうとした内容だったため、最終的にはこれを交渉テキストとすることで加盟国は合意に至りました。そして遂には、このテキストをベースとした最終的な交渉会合の中でも、この議長テキストの内容から大きく修正されることのないまま、最終的に条約としてまとまることとなったのです。おそらく、当時の議長が長年の議論を反映させたこのテキストを提示していなければ、今でも各国の懸隔が大きいまま条約の本格交渉すら始まっていなかったのではないかと思います。
なお、国際交渉においてテキストの骨子を提案する上では、上のWHOで触れたような「ゼロドラフト」だけではなく、「ノンペーパー」という名称で文書が回付されることもあります。「ゼロ」や「ノン」などと修飾語が付いているものの、これらは文書であって、さらには骨子どころではなく条文テキスト案そのものが記載されていることもあり、私も着任当初は文書の性質にひどく混乱したものでした。
5.如何にして交渉は終結するのか
交渉が合意または決裂した、という話はルール交渉以外でも聞く場面はあるでしょうが、交渉が合意してルールが作られるからには参加者全員が譲り合い納得するのが当然だろう、と思うかもしれません。もちろん全員が納得して合意に至れば理想的ですが、様々な立場の国々が参加するジュネーブの議論においては、それが常とは限りません。
WTOでは、意思決定はコンセンサス方式を原則とすることが条約で規定されています。コンセンサスで決められない場合には投票も認められていますが、これまでの閣僚会議でもコンセンサスで物事が決まってきました。これは、WTOの場合、知財だけでなく農業や漁業含め貿易に関する様々な分野の事項がカバーされるところ、2年に一度開催される閣僚会議での成果とすべく全体がパッケージとして交渉のディールになるという特徴に起因するといえます。自国としてはある分野で成果としたいものがあり、他国は知財分野において成果を求めているという状況では、たとえ自国が知財分野での当該成果を欲していなかったとしても、互いにある程度譲歩し合い、両方を交渉成果として成立させることがあり得ます(例えば上述の知財ウェイバー交渉の例)。投票となってしまえば自国の欲しい成果も得られない共倒れの可能性があるため、特にWTO閣僚会議の交渉最終段階では、こういったパッケージディールの集中的議論が行われ、最終的にコンセンサスに至る(ときには決裂する)ことになります。
WHOを含む各種国連機関も、基本的にはコンセンサスによる意思決定を慣行としているものの、WTOのように多種多様な分野のものが一挙に扱われるわけではないため、パッケージディールの必要性はそこまで高くありません。そのため、投票に至る可能性もそれなりに高く、実際、最近の各種国連関係の決議・決定に関するニュースでも投票という言葉を聞く機会もあったかと思います。ただし、単なる決議・決定の場合とは異なり、パンデミック条約交渉を含むルール交渉の場合には、それでもコンセンサスを追求する姿勢は依然として見られます。この理由の一つとして、条約・協定といったルールはあくまでその加盟国を拘束するものでしかないため、投票を経て合意してしまった条約・協定では賛成票を投じた加盟国しか加入せず実質的意味をなさないという点があります。一定の国際ルールを作り他国にそれを遵守してもらいたいと考えていても、当該国が加盟してくれなければルールは適用されないのです。そのため、ルール交渉の場合には、ある程度は妥協することで他国も納得して受け入れてくれるというコンセンサスの結末を目指す雰囲気が常にあります。
WIPOもWHOと同じ国連機関であり状況は同じなのですが、知的財産関係の条約というルールを多く所管していることもあり、コンセンサスへの拘りは一層強いように感じます。ただし、これは裏返せば投票への恐れとも言えます。最近ではこれに着目し、多数の国を有する地域グループ(=投票数も多い)が、投票の可能性をちらつかせ議論を有利に進めようとする場面も増えてきているのが現状です。WIPOのルール交渉においてはこれまで投票に至ったケースはないようですが、実際、今回の遺伝資源関連条約交渉の準備段階において、同志国との間の議論では、投票に至った場合にどうするか、投票に至らないためにはどう進めればいいか、と常に交渉戦略を練っていました。
交渉が終盤に差し掛かる中で、自国が孤立無援となってしまったらどう対処すれば良いでしょうか。自国以外はほぼコンセンサスに向け流れが出来上がってしまっているが、様々な要因のため自国として交渉結果は絶対に受け入れられない、だからといって反旗を翻して交渉決裂の原因として非難されるのは避けたいし、投票を要求しても勝ち目がない。交渉の中ではこんな状況に陥いることもあります。このような状況での最終手段としては、コンセンサスからの「離脱(dissociate)」という手段がとられることがあります。交渉が最終局面となりコンセンサスで決してしまいそうな瞬間挙手をして、「コンセンサスはブロックしないが、我々はコンセンサスからは離脱する」と宣言し、議事録に残すのです。結果として、交渉自体は「コンセンサスで合意した」ことになるのですが、実は全ての国が同意したわけではないという奇妙な状況が生まれます。一方で、交渉の成果はまとまり、離脱を表明した当該国としても対外的に上手く説明がつく、ということで双方に都合が良く、ジュネーブではこのような「離脱」が時折見られることになります。

(深夜3時に閉幕したWTO第12回閣僚会議)

(WIPO遺伝資源関係外交会議の署名式
Copyright: WIPO. Photo: Emmanuel Berrod. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)
ジュネーブでは国際機関においてほぼ毎日のように多数国間での議論が行われています。それは予算や各種プロジェクトに関するものであったり国際ルールの交渉であったり多種多様。中でも条約・協定といった国際ルールに関する交渉となると、各加盟国の法制度・実務や実体経済等に直接影響を及ぼすため、各国交渉団の熱量は生半可なものではありません。では、そのような交渉の経験が長年蓄積してきたジュネーブには、交渉を円滑に進めるための最適な手法というものは確立しているのでしょうか。
私は2021年秋に在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に赴任して以来、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)、さらには世界保健機関(WHO)において知的財産関連のルール交渉の場に参加する機会を得ました。その中で見いだせた上記問いに対する答えは、国際機関ごとに交渉の進め方は全く異なり統一的な交渉の進め方など存在しない、ということでした。各機関の所掌範囲や交渉目的等が異なるという側面は当然ありますが、今回は、知的財産ルール交渉への参加経験という狭い視点からとはいえ、ジュネーブにおけるWTO、WIPOそしてWHOでのルール交渉の現場について、簡単にご紹介できればと思います。
なお、本稿は特にWTOでのCOVID-19知財ウェイバー交渉、WIPOでの遺伝資源関連条約交渉、WHOでのパンデミック条約交渉への参加経験(2022~24年)に基づくものであり、ジュネーブの交渉全てに一般化できるものではない点ご容赦ください。それぞれの実体的交渉内容や日本としての考え方については、その紹介だけで長大になってしまうので、今回は紙面の都合上割愛します。
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)

(ジュネーブの国際機関が集まる地区にそびえるWIPO本部ビル)
2.真の交渉は大会議場の公式会合では起きていない
国際機関において最終的に条約や協定といった国際ルールに合意するには、当然ながらそれなりの会議場での公式会合といった正式な決定の場が必要です。ただ、その合意に至るための交渉も公式会合だけで済むのかといえば、全くそのようなことはありません。百数十もの国が加盟する国際機関において、公式な会合の場だけで議論が収束する可能性など極めて稀です。この点については、WTO/WIPO/WHOいずれの国際機関も共通しています。
交渉会期中に実際に交渉を進めるために何が重要かといえば、公式会合の合間等に実施される非公式会合であり、その形態は多種多様です。議論メンバーは変えず会合の名前だけ「非公式会合」としたものもあれば、議長が特定メンバーだけ招集する少数国会合、関心国同士での自発的な二国間協議などなど。このような非公式会合は、発言が記録に残らないこともあり、各国が率直に妥協点を探るための膝詰めでの交渉を可能にするのです。もちろん、交渉の前に、同志国同士の準備会合を行い戦略を練ったり、自国の味方を増やすための根回し会合を実施しておくことも不可欠です。
では、最終的な議論終結の機会以外に、公式会合とは一体どのような意味を持つのでしょうか。これも国際機関によって様々ですが、交渉団以外の者の傍聴も認められたり、その場での発言が正式なものとして受け取られるといった点で非公式会合と異なり得ます。特に後者に関しては、公式会合での発言が交渉記録として正式な議事録に残されるという場合があります。各国の交渉団はその国を代表して参加しているのであり、それぞれには各国の立場というものがあります。その立場を表明し議事録に記すことにより、自らの国がどのような立場で交渉に臨んでいるかを対外的に示すことができるのです。デメリットとして、そのために公式会合では政治的ポジションを記録に残すための言いっ放しの場にもなりがちで、何ら歩み寄りが見られない冗長な時間に感じられる部分は確かにあるのですが、一方で、後世においても発言が参照できるという点は重要です。一例として、交渉において条約・協定の文言についてせめぎ合いがある場合、双方が受け入れられるように敢えて解釈の余地を残す「建設的曖昧さ(constructive ambiguity)」という形で決着が図られることがあります。このとき、公式会合において「自国としてはこのように解釈している」といった形で発言し記録に残すことで、後々に解釈について争いとならぬよう根拠を残しておくという使い方もできるのです。

(WHOパンデミック交渉で発言する筆者)
上述のように、互いに妥協点を探る真の交渉を進める上では非公式会合の存在はほぼ必須となりますが、いつから、どの国を集めて、どこでそのような会合を行うのか、という点が問題となります。最初から少数国だけ集めようにも、誰がキープレイヤーか・何に関心があるかは全く分かりませんし、そのために交渉参加国全体の意見を聴き全体的な温度感や落としどころを見定めることは交渉成功のために重要であるとはいえ、いつまでも同じ政治的ポジションの発言を繰り返す国もあります。そのような中で単に「非公式会合」とだけ名前を変えて全員で議論をするだけでは、議論が進んでいきません。そのため、適切な段階で交渉論点のキープレイヤーとなる国を集め、真の着地点を見極めるための少数国調整を行うことが、交渉成功への鍵となります。
この少数国会合に関連し特に有名なのが、WTOの「グリーンルーム」と呼ばれる会合です。WTOウェブサイトの用語集にも掲載されていますが、これは事務局長の会議室に由来するもので、特に各国の交渉代表団トップのみ(状況によりプラス随行者1名)20~40名程度が参加できる会議です。交渉においてある程度論点が絞られ、そのキープレイヤーがぼんやりと特定できたあたりから、事務局長がグリーンルーム会合を招集して一気に議論の加速化や収束を図ることがあります。なお、グリーンルームの名前は、過去に事務局長会議室の壁等が本当に緑だったことに由来するようですが、今は緑ではないようです。また、WTO以外の場所で閣僚会議が開催される場合であっても、同様のハイレベル少数国会合がグリーンルーム会合と呼ばれるようになっています。
さらに際立った例として、WTOのCOVID-19ワクチン等に関する知財ウェイバー交渉時の進め方があります。この交渉においては、議論が尽くされ膠着状態に陥った際、交渉における極めて重要なプレイヤーと考えられた数か国に対し事務局長等が働きかけ、そのメンバー間のみで最初の合意テキスト案を検討させました。その結果ドラフトされたテキスト案が、その後少数国会議や全体会合に提示され、徐々に交渉メンバーの範囲を拡張するという手法を経て、最終的には閣僚決定として合意に至ることになりました。各国の立場が極めて離れていた本交渉の中で、交渉のキープレイヤーの中で率直に議論する場を作り、まずは核となる要素だけでも合意を得てしまう(要は、関心国だけで「握る」)ことが、確実な交渉成果に至る上で重要だったといえます。
もちろん、少数国会合には問題点もあります。特定の国だけで交渉を進めようとすると、蚊帳の外に置かれた国々は強い不満を抱きます。実際にWTOでの上記進め方は、透明性が欠如していると多くの国から批判を受けることにもなりました。これに対し対照的だったのがWHOパンデミック条約交渉です。この条約交渉はまだ継続中ではありますが、非公式会合という形であったとしても多くの交渉が交渉団全体で行われ、これまでのところWTOのグリーンルーム会合といったハイレベル少数国交渉はあまり聞くことがありません。これは、本条約が今後のパンデミックに対する予防・備え・対応を強化するためのもので、だからこそ知財に限らない広範な論点が多く、キープレイヤーが特定しにくいという課題もあったからかもしれません。とはいえ、キープレイヤーのみでの集中的議論の機会がない分、交渉は進みづらいともいえます。
こういったWTOやWHOでの交渉を横目に見ていたのか、WIPOの遺伝資源関連条約交渉はまさにその中道を通り、少数国会合と透明性の両立に腐心していました。同交渉では、まず議長は全体会合の場で交渉参加国に一通り発言させ、各交渉団の関心点やその度合いを見定めました。そして、そのままでは交渉局面が動かないと見るや、中規模会議室に非公式会合の場を移し、まずは各国からの物理的参加人数を制限。それでも参加国数が変わらず状況が打破できないと判断し、最終的には、メインテーブルに30~40名程度座れる小規模会議室を交渉部屋としました。これにより、発言できる物理的人数や国数が絞られ、率直な議論の空間を確保しました。一方、WTOのグリーンルーム等とは異なり、議長はキープレイヤーを指名することはせず、各地域グループ(WIPOには7つの地域グループがあります)にメインテーブル座席数を割り当てるに留めます。そして、誰が座り発言するかは地域グループ内で決定するよう判断を委ねて、議長としての中立性を徹底。加えて、発言者は同じ地域グループ内の国同士でローテーションし譲り合ってもよい仕組みとすることで、関心があるのに発言できないという不満を解消。さらにその交渉部屋の会合の様子は全体会合用の議場に投影し全員が傍聴できる仕組みとすることで、透明性の課題も克服されました。結果として、条約の交渉は無事にまとまった一方で、透明性についても各国から不平不満を聞かないという、バランスの取れた形で交渉が進められたように見えました。

(WIPOの大会議場)

(交渉終盤のWIPO小規模会議室)
最終的に条約・協定・決議・決定といったいずれの形を目指すにせよ、国際ルールに関する交渉であればベースとなるテキストがあり、それに基づいて交渉が行われます。では、交渉のベースとなるテキストは誰が用意するのでしょうか。
WTOの知財ウェイバー交渉では、当初、特定の国々からCOVID-19ワクチン等の知的財産保護義務の免除(=ワクチン等を知的財産で保護しない)の提案が出されました。しかしながら、この提案には当然ながら反対国も多く、これ自体では実体的なテキスト交渉が始まることすらありませんでした。提案内容に関し集中的議論は行ったものの、具体的な交渉ベースがなければ結局は空中戦のようなもので、案の定議論は膠着状態。そのような中、3.で触れたように状況を打開すべく事務局長が動き、交渉のキープレイヤー数か国に働きかけ対話を促した結果、その中で練られた結果が交渉テキストのベースとなったのです。このように、WTOの場合、キープレイヤーの間である程度合意できるような素地を先に作るという形で、交渉が進められたといえます。
WHOのパンデミック条約交渉の場合には、まずどのような要素がパンデミック対応のために必要なのか、という点から各国間で議論をスタートする必要がありました。様々な要素が含まれ得るためキープレイヤーの特定などほぼ不可能。そのため、議論の進行役であるビューローとWHO事務局は、加盟国へのアンケート等を通じて、まず「コンセプチュアル・ゼロドラフト」として条約のコンセプトを提示。これに対し出された意見を踏まえ、次に「ゼロドラフト」が公開されました。ここまでは、加盟国からの要望をすべて詰め込んだものという性質のテキストです。その後、更なる議論を経て複数のオプションへと整理された「ビューロー・テキスト」、それらへの意見を踏まえ中立的なものへ収斂させた「ネゴシエーション・テキスト」と、議論を経るたび出世魚のようにそのテキストの名前は次々に変化していきました。一方で、その内容も徐々に条約といえるような形へと進化。このいずれのテキストも、特定国ではなくビューロー・事務局側から提示されたものでしたが、これは、WHOでは条約のカバー範囲が広い上に交渉参加国のニーズだけに基づく各国提案自体では懸隔が大きすぎるため、議論全体の温度感を踏まえてビューロー・事務局が折衷案を作らざるを得なかったためといえます。
WIPOの遺伝資源関連条約交渉で交渉テキストとなったのは、関連委員会での議長(当時)が数年前に個人として提案した「議長テキスト」と呼ばれるものでした。これを交渉テキストとするか否かについても一悶着あったものの、この関連委員会では、議長テキスト提案に至るまでに20年強という長年の議論の蓄積がありました。さすが20年以上の議論を経ているだけあり、この議長テキストは加盟国全体の要望バランスを取ろうとした内容だったため、最終的にはこれを交渉テキストとすることで加盟国は合意に至りました。そして遂には、このテキストをベースとした最終的な交渉会合の中でも、この議長テキストの内容から大きく修正されることのないまま、最終的に条約としてまとまることとなったのです。おそらく、当時の議長が長年の議論を反映させたこのテキストを提示していなければ、今でも各国の懸隔が大きいまま条約の本格交渉すら始まっていなかったのではないかと思います。
なお、国際交渉においてテキストの骨子を提案する上では、上のWHOで触れたような「ゼロドラフト」だけではなく、「ノンペーパー」という名称で文書が回付されることもあります。「ゼロ」や「ノン」などと修飾語が付いているものの、これらは文書であって、さらには骨子どころではなく条文テキスト案そのものが記載されていることもあり、私も着任当初は文書の性質にひどく混乱したものでした。
5.如何にして交渉は終結するのか
交渉が合意または決裂した、という話はルール交渉以外でも聞く場面はあるでしょうが、交渉が合意してルールが作られるからには参加者全員が譲り合い納得するのが当然だろう、と思うかもしれません。もちろん全員が納得して合意に至れば理想的ですが、様々な立場の国々が参加するジュネーブの議論においては、それが常とは限りません。
WTOでは、意思決定はコンセンサス方式を原則とすることが条約で規定されています。コンセンサスで決められない場合には投票も認められていますが、これまでの閣僚会議でもコンセンサスで物事が決まってきました。これは、WTOの場合、知財だけでなく農業や漁業含め貿易に関する様々な分野の事項がカバーされるところ、2年に一度開催される閣僚会議での成果とすべく全体がパッケージとして交渉のディールになるという特徴に起因するといえます。自国としてはある分野で成果としたいものがあり、他国は知財分野において成果を求めているという状況では、たとえ自国が知財分野での当該成果を欲していなかったとしても、互いにある程度譲歩し合い、両方を交渉成果として成立させることがあり得ます(例えば上述の知財ウェイバー交渉の例)。投票となってしまえば自国の欲しい成果も得られない共倒れの可能性があるため、特にWTO閣僚会議の交渉最終段階では、こういったパッケージディールの集中的議論が行われ、最終的にコンセンサスに至る(ときには決裂する)ことになります。
WHOを含む各種国連機関も、基本的にはコンセンサスによる意思決定を慣行としているものの、WTOのように多種多様な分野のものが一挙に扱われるわけではないため、パッケージディールの必要性はそこまで高くありません。そのため、投票に至る可能性もそれなりに高く、実際、最近の各種国連関係の決議・決定に関するニュースでも投票という言葉を聞く機会もあったかと思います。ただし、単なる決議・決定の場合とは異なり、パンデミック条約交渉を含むルール交渉の場合には、それでもコンセンサスを追求する姿勢は依然として見られます。この理由の一つとして、条約・協定といったルールはあくまでその加盟国を拘束するものでしかないため、投票を経て合意してしまった条約・協定では賛成票を投じた加盟国しか加入せず実質的意味をなさないという点があります。一定の国際ルールを作り他国にそれを遵守してもらいたいと考えていても、当該国が加盟してくれなければルールは適用されないのです。そのため、ルール交渉の場合には、ある程度は妥協することで他国も納得して受け入れてくれるというコンセンサスの結末を目指す雰囲気が常にあります。
WIPOもWHOと同じ国連機関であり状況は同じなのですが、知的財産関係の条約というルールを多く所管していることもあり、コンセンサスへの拘りは一層強いように感じます。ただし、これは裏返せば投票への恐れとも言えます。最近ではこれに着目し、多数の国を有する地域グループ(=投票数も多い)が、投票の可能性をちらつかせ議論を有利に進めようとする場面も増えてきているのが現状です。WIPOのルール交渉においてはこれまで投票に至ったケースはないようですが、実際、今回の遺伝資源関連条約交渉の準備段階において、同志国との間の議論では、投票に至った場合にどうするか、投票に至らないためにはどう進めればいいか、と常に交渉戦略を練っていました。
交渉が終盤に差し掛かる中で、自国が孤立無援となってしまったらどう対処すれば良いでしょうか。自国以外はほぼコンセンサスに向け流れが出来上がってしまっているが、様々な要因のため自国として交渉結果は絶対に受け入れられない、だからといって反旗を翻して交渉決裂の原因として非難されるのは避けたいし、投票を要求しても勝ち目がない。交渉の中ではこんな状況に陥いることもあります。このような状況での最終手段としては、コンセンサスからの「離脱(dissociate)」という手段がとられることがあります。交渉が最終局面となりコンセンサスで決してしまいそうな瞬間挙手をして、「コンセンサスはブロックしないが、我々はコンセンサスからは離脱する」と宣言し、議事録に残すのです。結果として、交渉自体は「コンセンサスで合意した」ことになるのですが、実は全ての国が同意したわけではないという奇妙な状況が生まれます。一方で、交渉の成果はまとまり、離脱を表明した当該国としても対外的に上手く説明がつく、ということで双方に都合が良く、ジュネーブではこのような「離脱」が時折見られることになります。

(深夜3時に閉幕したWTO第12回閣僚会議)

(WIPO遺伝資源関係外交会議の署名式
Copyright: WIPO. Photo: Emmanuel Berrod. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)
6.おわりに
上で述べたほかにも、様々な思惑渦巻く各国交渉団達の中で議長がどのように交渉の舵取りを行ったのか、テキストの文言修正は実際にどのように反映されていくのか、交渉内容のリークはどこからどのようにして発生するかなど、他にも興味深い交渉側面は枚挙にいとまがありません。しかしながら、今回は分量の関係上ここで紹介をとめることといたします。
ジュネーブの国際機関では、ゼロではない「ゼロドラフト」が、「ノンペーパー」という名のペーパーで回付され、グリーンではない「グリーンルーム」での議論を経由して、全会一致とは限らない「コンセンサス」で合意に至る、そんな不思議な交渉が日々行われています。今のところ交渉に最適解というものは存在せず、これからも様々な形態を試みながら交渉が進められていくことでしょう。交渉、というとその実体面のみにフォーカスされがちですが、たまには息抜きにでも、交渉の形、という観点からジュネーブの交渉を眺めてみるのも面白いかもしれません。
上で述べたほかにも、様々な思惑渦巻く各国交渉団達の中で議長がどのように交渉の舵取りを行ったのか、テキストの文言修正は実際にどのように反映されていくのか、交渉内容のリークはどこからどのようにして発生するかなど、他にも興味深い交渉側面は枚挙にいとまがありません。しかしながら、今回は分量の関係上ここで紹介をとめることといたします。
ジュネーブの国際機関では、ゼロではない「ゼロドラフト」が、「ノンペーパー」という名のペーパーで回付され、グリーンではない「グリーンルーム」での議論を経由して、全会一致とは限らない「コンセンサス」で合意に至る、そんな不思議な交渉が日々行われています。今のところ交渉に最適解というものは存在せず、これからも様々な形態を試みながら交渉が進められていくことでしょう。交渉、というとその実体面のみにフォーカスされがちですが、たまには息抜きにでも、交渉の形、という観点からジュネーブの交渉を眺めてみるのも面白いかもしれません。