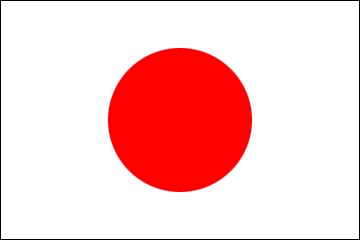代表部の仕事:貿易と開発・貿易のための援助
令和6年6月10日
貿易と開発・貿易のための援助
舟杉 秀平 二等書記官
1 初めに
私は、2022年7月から、ジュネーブ代表部において、主に世界貿易機関(WTO)の会合をフォローする経済部に所属しています。WTOの中でも、私は開発関連会合、投資円滑化協定交渉、複数の分野にまたがる横断的事項などを担当してきました。
この記事では、(1)国際機関の会合での一般的な業務の流れ、(2)担当として対応してきたWTOにおける開発関連の会合、(3)日本の貿易関連援助についてご紹介します。
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)
2 国際機関代表部における会合対応業務
まず、国際機関代表部での会合対応についてご紹介します。
国際機関代表部は、各国際機関に対して日本国を代表し、国際機関への意思決定や審議、ルール交渉等を行っています。様々なテーマや様々な形態(担当級から大使級、少数国や有志国等々)で開催される会合をペース・メーカーとして業務にあたっています。会合対応に際しては、事前に準備をした上で、当日対応、記録作成、次回会合の対応検討という流れが一般的です。
私は、2022年7月から、ジュネーブ代表部において、主に世界貿易機関(WTO)の会合をフォローする経済部に所属しています。WTOの中でも、私は開発関連会合、投資円滑化協定交渉、複数の分野にまたがる横断的事項などを担当してきました。
この記事では、(1)国際機関の会合での一般的な業務の流れ、(2)担当として対応してきたWTOにおける開発関連の会合、(3)日本の貿易関連援助についてご紹介します。
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)
2 国際機関代表部における会合対応業務
まず、国際機関代表部での会合対応についてご紹介します。
国際機関代表部は、各国際機関に対して日本国を代表し、国際機関への意思決定や審議、ルール交渉等を行っています。様々なテーマや様々な形態(担当級から大使級、少数国や有志国等々)で開催される会合をペース・メーカーとして業務にあたっています。会合対応に際しては、事前に準備をした上で、当日対応、記録作成、次回会合の対応検討という流れが一般的です。
会合対応に備え、まずは、日本の基本的な立場を本省と協力して検討します。また、並行して各分野で考えの近い立場の国や、異なる立場の国の見解を事前に聴取し、日本として何を発言すべきかを検討していきます。会合本番では、議論の流れに合わせて内容を微調整しつつ、適切なタイミングで発言しつつ記録を作成します。作成した記録を公電の形で本省に共有し、次の会合へ備えるといったサイクルになっています。


(会合に出席する筆者) (開発有志国での集まりの様子)
3 WTOにおける開発関連会合
次に、主に担当してきたWTOにおける開発関連会合についてご紹介します。
WTOでは、貿易と開発委員会(Committee on Trade and Development:CTD)という委員会を中心に、途上国の貿易政策や途上国の貿易支援についての議論が行われています。
次に、主に担当してきたWTOにおける開発関連会合についてご紹介します。
WTOでは、貿易と開発委員会(Committee on Trade and Development:CTD)という委員会を中心に、途上国の貿易政策や途上国の貿易支援についての議論が行われています。

(貿易と開発委員会開始前の議場の様子)
貿易と開発委員会(CTD)に加え、様々な関連会合があり、例えば、貿易と援助について各国の取組を紹介したり、どのような支援が適切かを検討したりする貿易のための援助(Aid for Trade)会合や、後発発展途上国(Least Developed Countries:LDC)の貿易状況・政策等について検討するLDC小委員会があります。
その他にも、途上国への特恵関税に関する会合や綿花援助に関する会合、技術移転に関する作業部会等、一口に開発と言っても様々な角度で途上国の貿易関連政策や貿易状況を検討する会合があります。これらの開発を専門とする委員会に加え、各協定の委員会やWTOの組織でも、途上国についての議論が行われています。
また、開発に関する議論は、担当級の会合にとどまりません。
WTOでは、約2年に一度、閣僚会議(Ministerial Conference:MC)が開催されます。直近では、2024年2月に、アラブ首長国連邦において、第13回閣僚会議(MC13)が開催されました。MC13でも、開発は主要分野の一つとして閣僚級での議論が行われ、また、多くの開発関連のサイド・イベントも開催されました。MC13では、東ティモール、コモロ共和国のWTOへの新規加盟や、これまで進展の乏しかった、途上国への特別措置に関する閣僚宣言やLDCからの卒業国への移行支援決定等など、開発側面での進展を得ることができました。

(MC13全体会合の様子)
MC13での開発成果を踏まえ、カメルーンにおいて開催予定のMC14へ向けて、開発分野での議論が再開されています。
4 貿易と開発援助での日本の貢献
ここからは、貿易のための援助会合に焦点を当てつつ、日本の貿易開発支援への貢献について紹介します。
WTOには、貿易のための援助(Aid for Trade)という取組の枠組みがあります。これは、各国や他の国際機関が行っている貿易関連の支援全般について現状の分析やレビュー、各支援の現状の紹介が行われる枠組みです。
貿易のための援助(Aid for Trade)では、各国の貿易関連支援の分析・評価が行われており、日本は、貿易に貢献する支援において、世界銀行に次いで2位、単独の国としては1位を占めてきています。
日本はWTOや国際貿易センター(ITC)を通じて、多国間の枠組みで途上国の支援を行ってきています。
WTOについて、日本は、ドーハ開発基金という途上国の貿易能力強化支援を目的に2002年に設立された基金に拠出しています。この基金は、主に、発展途上国・LDCのWTO関連協定履行の支援のために使われています。支援を実際に行うのは、WTOの技術支援部(ITTC)という部署で、各国のニーズを踏まえ、WTOルールを円滑に履行していくための支援を行っています。途上国・LDCがWTOルールを履行することは、貿易の予見可能性を向上させることを通じ、途上国自身のみならず、国際貿易全体に良い影響を与えることが期待されます。
国際貿易センター(ITC)は、WTOとUNCTADの資金拠出を受けて設立された国際機関で、国連システムの中で貿易促進分野の技術支援協力のフォーカルポイントとして指定されています。途上国の貿易促進・援助の文脈において、ITCは非常に重要かつ意味のある役割を果たしています。日本からもこれまで、継続的に様々な案件に拠出しており、2023年は、ウクライナにおける電子商取引拡大支援事業、女性起業家の貿易参画推進事業、スリランカ企業の輸出促進事業を支援してきました。
4 貿易と開発援助での日本の貢献
ここからは、貿易のための援助会合に焦点を当てつつ、日本の貿易開発支援への貢献について紹介します。
WTOには、貿易のための援助(Aid for Trade)という取組の枠組みがあります。これは、各国や他の国際機関が行っている貿易関連の支援全般について現状の分析やレビュー、各支援の現状の紹介が行われる枠組みです。
貿易のための援助(Aid for Trade)では、各国の貿易関連支援の分析・評価が行われており、日本は、貿易に貢献する支援において、世界銀行に次いで2位、単独の国としては1位を占めてきています。
日本はWTOや国際貿易センター(ITC)を通じて、多国間の枠組みで途上国の支援を行ってきています。
WTOについて、日本は、ドーハ開発基金という途上国の貿易能力強化支援を目的に2002年に設立された基金に拠出しています。この基金は、主に、発展途上国・LDCのWTO関連協定履行の支援のために使われています。支援を実際に行うのは、WTOの技術支援部(ITTC)という部署で、各国のニーズを踏まえ、WTOルールを円滑に履行していくための支援を行っています。途上国・LDCがWTOルールを履行することは、貿易の予見可能性を向上させることを通じ、途上国自身のみならず、国際貿易全体に良い影響を与えることが期待されます。
国際貿易センター(ITC)は、WTOとUNCTADの資金拠出を受けて設立された国際機関で、国連システムの中で貿易促進分野の技術支援協力のフォーカルポイントとして指定されています。途上国の貿易促進・援助の文脈において、ITCは非常に重要かつ意味のある役割を果たしています。日本からもこれまで、継続的に様々な案件に拠出しており、2023年は、ウクライナにおける電子商取引拡大支援事業、女性起業家の貿易参画推進事業、スリランカ企業の輸出促進事業を支援してきました。

(ウクライナにおける電子商取引拡大支援事業に関する、MC13での文書交換式の様子。提供:国際貿易センター(ITC))
上述の貿易のための援助において日本が第1位の支援国となっている背景には、WTOドーハ開発基金や国際貿易センターへの拠出といった、このような国際機関や多国間での支援に加えて、二国間での貿易関連インフラや技術支援を積み重ねてきていることがあります。こうした個別の努力が日本のWTOにおける開発の文脈におけるプレゼンスの向上にもつながっています。
WTOの貿易のための援助の枠組みでは、2年に一度、各国の貿易関連支援を振り返り、評価するAid for Tradeグローバル・レビューが開催されます。このイベントは、WTO事務局がOECDと協力して、2年間の支援の分析を行い、報告書が発出されます。また、WTOの各加盟国がテーマを持ち寄って多くのセッションが開催されます。

(2022年のグローバル・レビューの様子。提供:WTO事務局)
今年は2年に一度のグローバル・レビュー開催の年に当たり、6月26日から28日にWTOで開催予定です。日本も電子商取引分野における支援とAIの活用をテーマとしたセッションを予定しています。関心がある方は、以下のURLから会合の様子を御覧ください。
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review24_e/global_review24_e.htm
4 最後に
WTOが開発援助に特化した国際機関ではない中、途上国の貿易推進のために何ができるかという点は常に難しい論点となっています。今後、ますます開発の議論の重みがWTOにおいて増していく中、WTO協定や既存の支援を踏まえ、追加の規律の柔軟性や支援がどのような理由や目的で、どのようなものが必要なのか、どのような効果があるのか、といった実践的な観点から、各WTOメンバーが国際貿易から一層利益が得られるのかについての議論を進めていくことが求められます。
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review24_e/global_review24_e.htm
4 最後に
WTOが開発援助に特化した国際機関ではない中、途上国の貿易推進のために何ができるかという点は常に難しい論点となっています。今後、ますます開発の議論の重みがWTOにおいて増していく中、WTO協定や既存の支援を踏まえ、追加の規律の柔軟性や支援がどのような理由や目的で、どのようなものが必要なのか、どのような効果があるのか、といった実践的な観点から、各WTOメンバーが国際貿易から一層利益が得られるのかについての議論を進めていくことが求められます。