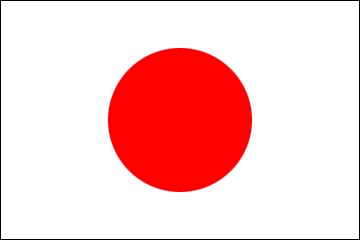代表部の仕事:「WTOは死んだ」と言われたルール交渉の現場から
令和7年7月17日
「WTOは死んだ」と言われたルール交渉の現場から
赤井 啓嗣 一等書記官
(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)
ここでは、私が3年間取り組んできたWTO漁業補助金交渉について少しご紹介したいと思います。
まず皆さん、世界全体でどのくらい魚をどのくらい獲って食べているでしょうか?昭和30年代には3千万トンだったものが、私が生まれた昭和60年に8千万トン程度に達し、実はこれ以降40年間、ほぼ横ばいで推移しています。
この理由については、養殖生産の拡大など、いくつかの見方があると思いますが、「既に地球全体で供給し得る水産物の限界量に達している」と見ることもできるかもしれません。水産資源の持続可能性確保のため、また、日本の食料安全保障のため、世界全体で資源管理に取り組んでいくことが求められています。
一方、WTOの場でこう言うと、途上国を中心に「まずは、大規模補助金国、大規模生産国、遠洋漁業国など、資源の枯渇に歴史的責任を負うメンバーが漁獲能力を削減すべし」と来るのが定石です。
少数国のみの間で厳しいルールを策定し、自らこれに服することも確かに可能ではあります。しかしながら、魚は国境を跨いで回遊します。そうではないところで乱獲が起きては、持続可能性確保という目的は達成されません。またそもそも、そうではないところを野放しにし、自らにのみ厳しい規律を課すことは、国益にもなりません。世界全体での資源管理を促すマルチのルールが必要です。
また、WTOは、「世界貿易機関」の名のとおり、補助金等の貿易に影響を与える各国の政策に関するルール作りの機関であって、メンバーに対して直接、漁獲可能量を割り当て、遵守させることは想定されていないことにも留意する必要があります。
こうしたことを踏まえ、日本はWTOにおいて以下のような主張を展開しています。
もちろん日本の主張のみが通るわけではありません。166ものメンバーがWTOに加盟していますので、166通りの考え方があります。また、意思決定は全会一致(コンセンサス)によりなされます。それでも、日本の主張が概ね反映された形で現在の交渉は推移しています。
3年を振り返ると、一番思い出深いのは、2024年2月末にアブダビで行われた第13回閣僚会合(MC13)での交渉です。直前の1か月間は、「漁業マンス(月間)」と称して休日返上で交渉が行われました。アブダビの現場では、深夜1時に少数国会合が招集されたこともありました。残念ながら2~3か国の反対により最終的には合意には至りませんでしたが、交渉現場を預かる身として、本当にあと一歩だったという実感があります。
バイ(二国間)やプルリ(複数国間)に再度注目が集まりがちな時勢ですが、「マルチのルール」の重みも幾分かあるように思います。特に、環境問題など今日的な課題に対し、WTOが答えを出していくことが求められます。自らの任期中には実現できませんでしたが、後任の時代に「漁業補助金交渉」に決着がつき、「WTOのルール形成機能は健在」と報じられることを東京から期待したいと思います。
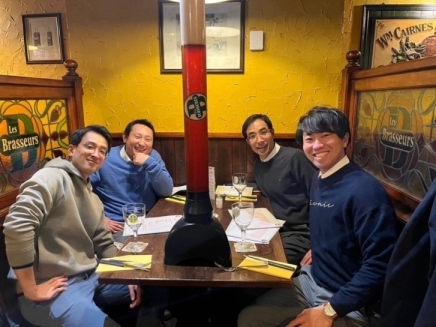
【1週間の交渉を終え関係者と次回に向けた戦略練り直しを行う一幕】
ここでは、私が3年間取り組んできたWTO漁業補助金交渉について少しご紹介したいと思います。
まず皆さん、世界全体でどのくらい魚をどのくらい獲って食べているでしょうか?昭和30年代には3千万トンだったものが、私が生まれた昭和60年に8千万トン程度に達し、実はこれ以降40年間、ほぼ横ばいで推移しています。
この理由については、養殖生産の拡大など、いくつかの見方があると思いますが、「既に地球全体で供給し得る水産物の限界量に達している」と見ることもできるかもしれません。水産資源の持続可能性確保のため、また、日本の食料安全保障のため、世界全体で資源管理に取り組んでいくことが求められています。
一方、WTOの場でこう言うと、途上国を中心に「まずは、大規模補助金国、大規模生産国、遠洋漁業国など、資源の枯渇に歴史的責任を負うメンバーが漁獲能力を削減すべし」と来るのが定石です。
少数国のみの間で厳しいルールを策定し、自らこれに服することも確かに可能ではあります。しかしながら、魚は国境を跨いで回遊します。そうではないところで乱獲が起きては、持続可能性確保という目的は達成されません。またそもそも、そうではないところを野放しにし、自らにのみ厳しい規律を課すことは、国益にもなりません。世界全体での資源管理を促すマルチのルールが必要です。
また、WTOは、「世界貿易機関」の名のとおり、補助金等の貿易に影響を与える各国の政策に関するルール作りの機関であって、メンバーに対して直接、漁獲可能量を割り当て、遵守させることは想定されていないことにも留意する必要があります。
こうしたことを踏まえ、日本はWTOにおいて以下のような主張を展開しています。
- 漁業補助金そのものが直ちに問題というわけではない。例えば漁港整備や、資源調査、地球温暖化に対応した漁船への転換の意義は、広く認識されるはず。
- 重要なことは、資源に負荷がかかるおそれがある補助金を支出する際には、それ相応の資源管理を行った上で、その旨の説明責任を果たすこと。これを世界全体の漁業補助金のルールとしてはどうか。
- また、WTOでは、マルチの枠組みであることを活かし、上記の説明が十分かどうか、世界全体の目でチェックすることとしてはどうか。
- 海洋国家である日本は、資源管理、説明責任をしっかり果たす用意がある。世界全体での資源管理を促進するため、途上国へのサポートにも汗をかく用意がある。
もちろん日本の主張のみが通るわけではありません。166ものメンバーがWTOに加盟していますので、166通りの考え方があります。また、意思決定は全会一致(コンセンサス)によりなされます。それでも、日本の主張が概ね反映された形で現在の交渉は推移しています。
3年を振り返ると、一番思い出深いのは、2024年2月末にアブダビで行われた第13回閣僚会合(MC13)での交渉です。直前の1か月間は、「漁業マンス(月間)」と称して休日返上で交渉が行われました。アブダビの現場では、深夜1時に少数国会合が招集されたこともありました。残念ながら2~3か国の反対により最終的には合意には至りませんでしたが、交渉現場を預かる身として、本当にあと一歩だったという実感があります。
バイ(二国間)やプルリ(複数国間)に再度注目が集まりがちな時勢ですが、「マルチのルール」の重みも幾分かあるように思います。特に、環境問題など今日的な課題に対し、WTOが答えを出していくことが求められます。自らの任期中には実現できませんでしたが、後任の時代に「漁業補助金交渉」に決着がつき、「WTOのルール形成機能は健在」と報じられることを東京から期待したいと思います。
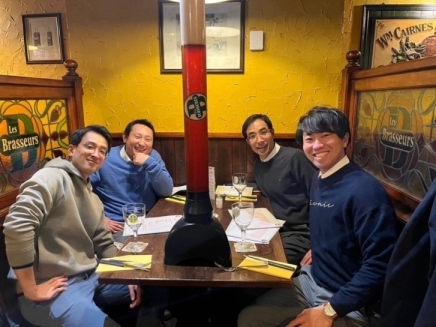
【1週間の交渉を終え関係者と次回に向けた戦略練り直しを行う一幕】