代表部の仕事:国際自然保護連合(IUCN)の活動
令和3年5月26日
国際自然保護連合(IUCN)の活動
中西 枝里子 専門調査員
私は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の専門調査員として、環境分野の中でも、生物多様性に関する業務を担当しています。「生物多様性」というと、難しい言葉だと思われるでしょうか。ジュネーブの郊外のグランに本部を置く「国際自然保護連合(International Union for Conservation of Nature: IUCN)」のある専門家は、一般の方に話すときは「生物多様性」という言葉は使わず、単に「自然」と言うのだそうです。「自然とは本来、人々にとって身近で親しみあるものなのに、私たち専門家が、堅苦しい用語を使って人々と自然の間に距離を作ってしまっている。」と言っていたのが、とても印象に残っています。地球には、3000万種とも言われる、多様な植物や動物、微生物などが存在しています。これらの多様な生物が関与しあう絶妙なバランスの上に自然は成り立っており、この「自然の豊かさ」のことを生物多様性と呼びます。この生物多様性が私たちの暮らしにどのような影響を与えているのか、コウモリを例にとって説明しつつ、IUCNの活動を紹介したいと思います。
IUCNは、自然に関する保護活動、研究、ルール・基準作りなどをする国際機関で、各国政府をはじめ、政府機関やNGO等が会員となっています。世界中の生物学者の協力により、地球上の動植物の種の生息域や生態と保存状況(絶滅のおそれの有無やその程度)を取りまとめたリスト(通称レッドリスト)を作成していることが、特に知られています。2021年5月1日現在、レッドリストには5940種の哺乳類が掲載されており、このうち22%を占める1321種がコウモリ目です。コウモリ目より多いのはネズミ目だけで、哺乳類全体の40%を占める2365種が掲載されています。
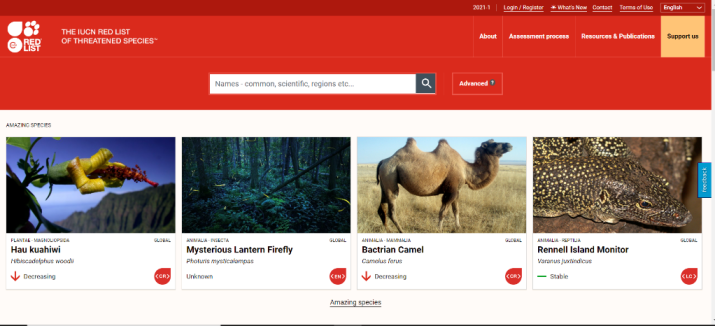
国際自然保護連合(IUCN)ホームページ内のレッドリスト
新型コロナウイルス(COVID-19)の原因となるウイルスは、コウモリ起源の可能性も示唆されています。エボラ出血熱、SARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)など、近年世界を脅かした新しい感染症の多くがコウモリを起源としていたということで、コウモリを宿主とする病原体が注目されています。コウモリから人にうつる病気として最も 一般的なのは、狂犬病です。狂犬病は、犬だけでなく、人やコウモリを含めた全ての哺乳類に感染するウイルス性の病気です。こうした、動物と人に共通の感染症には家畜由来のものが多くありますが、COVID-19のような新しい人獣共通感染症の中には、野生動物由来のものも増えているようです。ある動物が持っていた病気が、種の壁を超えて人や他の動物にうつる過程は目に見えないミクロの世界で起こっており、その原理はまだ解明されていません。しかし、ドイツに本部を置く「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)」は、人間の活動が野生動物の生息地に進入して、人や家畜と野生動物の接点が増えた結果、野生動物由来の新しい感染症が増えた、と警告しています(報告書)。

COVID19の起源である可能性が高いキクガシラコウモリ © Paul Dickson
もともと、コウモリは体内に病原体を多く持っているのに、それによって病気になったり死んだりすることが少ないことが知られていました。その理由については様々な説がありますが、コウモリには多くの種があり、その分、体内に持っている病原体の種類も多いことが一因であると考えられます。また、コウモリは体が小さい割に寿命が長く、これが病原体の多さに関係しているのではないかという説もあります。コウモリは渡り鳥のように長距離を移動するので、各地で様々な病原体に触れることも理由の一つでしょう。また、洞窟などの狭い場所で、数百~数千匹の群れで暮らしており、これはウイルスの感染が広がりやすい「三密」状態です。しかし、イメージがあまり良くないからか、コウモリの研究はあまり進んでいない中、IUCNのコウモリ専門家グループでは、謎の多いコウモリの生態について日々最新の研究結果を共有し、議論を進めています。

それでは、多くの病原体を持っているコウモリはいなくなった方がいいのでしょうか。実はコウモリは、病害虫抑制と受粉という、二つの役割で私たちの暮らしを支えています。コウモリは、大きく分けてココウモリとオオコウモリに分類されますが、ココウモリは、虫を餌とする種がほとんどで、大群を成し、蛾や蚊などの害虫を大量に食べています。アメリカにおけるコウモリによる病害虫抑制の経済的価値を、一年間で37億ドル(約4030億円)とする推計がありますが、実際には病害虫対策にこのような大金を投じることは不可能なので、コウモリには計りしれない価値があると言えます。他方、オオコウモリは主に熱帯地域に生息し、果実や花の蜜を餌としています。熱帯地域の300~500種程の植物が、繁殖をコウモリによる受粉に頼っています(出典1、2)。こうした植物には、バナナやマンゴーなどの熱帯果実や、実は化粧品やお酒の原料となっているサボテン科の植物などが含まれます。
自然は私たちに水や食料を提供しているだけでなく、たとえば健全な森林や土壌は洪水や土砂崩れを防ぎ、大気汚染を浄化します。こうした自然の恵みを「生態系サービス」と呼びますが、コウモリによる病害虫抑制や受粉もその一部です。IUCNでは、生物の種の研究・保全活動をするだけでなく、自然を保護してその生態系サービス機能を最大限に引き出すことで、同時に災害や食料生産などにおける人間の社会的課題も解決していこうという取り組みも行っています。これを、自然を基盤とした解決策(Nature-based Solutions: NbS)と呼び、IUCNは2020年7月にNbS国際基準を策定しました。(日本では昔から、農村に接する森林や農地、ため池など、自然の保護と人間の活動が一体化した「里山」という概念や、防潮林・防風林を活用した自然の力を借りた防災など、NbSに通じる自然共生の歴史があり、またこうした取り組みを海外に広めるための活動(SATOYAMAイニシアティブやEcoDRRなど)にも取り組んできており、IUCNの会議で成功事例を紹介したり、国際基準の利点や改善点を他国と話し合ったりしています。)
2021年9月には、IUCNの総会である世界自然保護会議がフランスのマルセイユで開催されます。パンデミックを受け、オンラインで一般の方々が参加できる内容が豊富に用意される予定ですので、のぞいてみてはいかがでしょうか。
自然は私たちに水や食料を提供しているだけでなく、たとえば健全な森林や土壌は洪水や土砂崩れを防ぎ、大気汚染を浄化します。こうした自然の恵みを「生態系サービス」と呼びますが、コウモリによる病害虫抑制や受粉もその一部です。IUCNでは、生物の種の研究・保全活動をするだけでなく、自然を保護してその生態系サービス機能を最大限に引き出すことで、同時に災害や食料生産などにおける人間の社会的課題も解決していこうという取り組みも行っています。これを、自然を基盤とした解決策(Nature-based Solutions: NbS)と呼び、IUCNは2020年7月にNbS国際基準を策定しました。(日本では昔から、農村に接する森林や農地、ため池など、自然の保護と人間の活動が一体化した「里山」という概念や、防潮林・防風林を活用した自然の力を借りた防災など、NbSに通じる自然共生の歴史があり、またこうした取り組みを海外に広めるための活動(SATOYAMAイニシアティブやEcoDRRなど)にも取り組んできており、IUCNの会議で成功事例を紹介したり、国際基準の利点や改善点を他国と話し合ったりしています。)
2021年9月には、IUCNの総会である世界自然保護会議がフランスのマルセイユで開催されます。パンデミックを受け、オンラインで一般の方々が参加できる内容が豊富に用意される予定ですので、のぞいてみてはいかがでしょうか。
