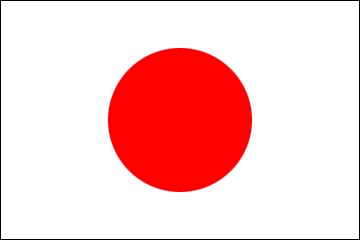ジュネーブの国際機関で活躍する日本人職員(WTO事務局ルール部 参事官 矢野博巳さん)

【WTO事務局ルール部 参事官 矢野博巳さん】
2003年からWTO事務局で勤務している矢野博巳さん(ルール部参事官)に、日々の仕事の様子や国際機関で働くことの魅力等について伺いました。
Q1 現在の仕事の内容は?
WTOは、例えて言えば、国際貿易の世界において、立法・司法・行政に当たる3つの機能を果たしています。つまり、ルールメーキング、貿易裁判(紛争解決)及び既存ルールの執行です。ルール部はこの全てに関わっています。WTOの紛争では、敗訴した国が判決に従わない場合の制裁の手続について詳細に定めてあり、他の国際機関と比べて特徴的な点となっています。なお、最近では途上国支援もWTOの重要な仕事の一つとなっており、4番目の機能と言うこともできます。私は主に、アンチダンピング、補助金相殺関税、セーフガードという「貿易救済」に関する仕事をしています。もちろん、日本政府の代表としてではなく、多角的貿易体制を維持する国際公務員という中立の立場としてです。ルールメーキング及び既存ルールの執行は加盟国が主導する立場(メンバー・ドリブン)であって、我々事務局員は加盟国の議論のサポート役に回ります。紛争解決というのは、ある国が他国の例えば貿易救済措置がWTO協定違反であるとして提訴したときに、当該紛争に関する判決を下す機能ですが、その裁判官の役割を果たす「パネリスト」の補佐を我々は行います。
Q2 WTOで働こうと思ったきっかけは?
元々霞が関で国家公務員として働いており、1998年から2002年までジュネーブの日本政府代表部にも勤務していました。その当時、仕事の相手であるワシントンやブラッセルの役人と議論していて、彼らは専門家であり、日本でありがちな、広く薄くという知見では歯が立たないなと痛感したことが原体験です。世界を舞台にする専門家としてキャリアを積みたいと考えていた時にたまたまWTO事務局に求人募集が出ていることを知り、応募したというわけです。
Q3 やりがいや苦労は?
特定の国の立場を離れ、多角的貿易体制の適切な運営という比較的高い視点から世界を見られることは大きな魅力です。また、職場は典型的な多文化環境で、色々な国の出身の優秀な人々が同僚なので、仕事を離れても、日本からは見えにくい世界の動き、例えば中東の生々しい情勢といったことが日常的に話題に出て、得難い経験です。苦労としては、日本とは文化・考え方が違うことに戸惑うことでしょうか。私の部はアメリカ的な文化なので、若い人も積極的に議論に参加します。例えば駆け出しのインターンが「私は矢野さんの意見に反対です」と言ってきます。「インターンは黙っていなさい」と言うのではなく、間違っているならなぜ間違っているかをこちらがちゃんと説明しないといけません。そういう意味では慣れが必要な部分はありますね。
Q4 日本で若者の内向き傾向が指摘されて久しいが?
私の部の同僚たちは主にロイヤー(法律家)ですが、彼らは法律家になりたいのと同時に自国の枠にこだわらずに国際的な場で仕事がしたいと考えて国際法・WTO法を勉強し、WTOのロイヤーのポストに応募したという人がほとんどです。一方日本では、日本の外で仕事を探しても良いと考える大学生は少ないですね。これは法学部に限らないようです。日本国内に良い就職先が沢山あるのであえて海外で働きたいと思わないということかも知れません。しかし、自分たちの将来の選択肢を意図的に狭める必要はないでしょう。より良い仕事、やりがいのある仕事を、世界中の広い選択肢から選ぶという発想がもっとあって良いと思います。世界の多くの若者はそうしていますから。

セーフガード委員会の議場における矢野参事官(一番左)
※本インタビューは,「我が国の経済外交2018」(外務省経済局著,日本経済評論社発行(2018年01月))に掲載されています。