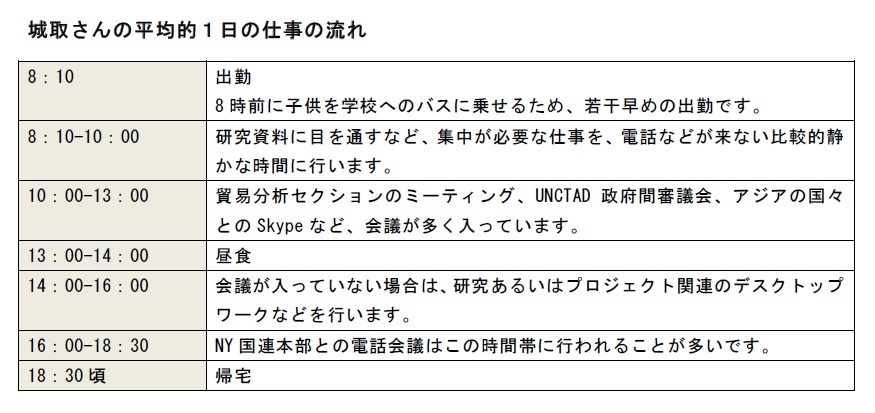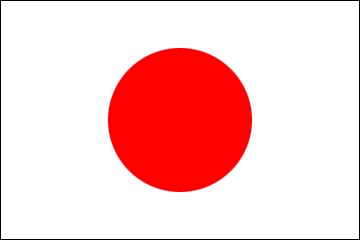ジュネーブの国際機関で活躍する日本人職員(国連貿易開発会議(UNCTAD) 城取 美保さん)
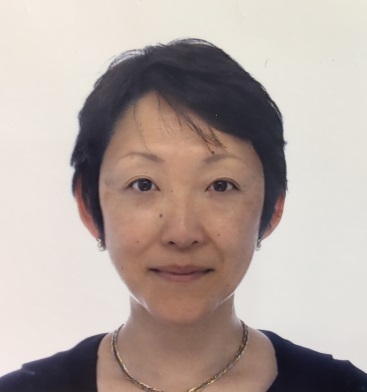
【国際貿易部 貿易政策分析セクションチーフ・上級エコノミスト 城取 美保さん】
Q1 所属機関の役割や目的について教えて下さい。
ジュネーブは、貿易問題を審議する世界の中心地です。そして「貿易」は経済開発に欠かせない「エンジン」であると、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が認めています。私の働く国連貿易開発会議(UNCTAD)は、「貿易と開発」の分野で国連システムのフォーカルポイントと位置付けられており、貿易や投資を通じた持続可能な開発について、研究、各国間の会議、そして技術協力を行っています。

Q2 現在の仕事について教えて下さい。
UNCTADに勤務して26年目になります。2015年からは貿易政策分析セクションの上級エコノミストとして働いています。世界の輸出入の動向や貿易政策のデータを分析し、途上国の社会と経済発展に及ぼす効果を研究しています。2015年に「2030アジェンダ」が決定して以降は、UNCTADを代表して国連の他機関との連携に参加することが増えました。国連全体の枠組みの中で、持続可能な開発を促す貿易政策について、国連総会や各国に提言しています。
この仕事の醍醐味のひとつは、エコノミストとして常に第一線の研究対象に取り組めることだと思います。たとえば、21世紀に入って貿易政策の定義が大きく変わりました。20世紀の輸出入は会社間の取引でしたが、現在の世界の貿易の約40%かそれ以上がグローバル.バリュー.チェーン(GVC)を通じた会社内取引と言われています。たとえばユニクロのようなブランドが管轄するGVCのなかで、A国が輸出した綿糸で、B国の工場が綿生地を織り、染色裁断したものを、C国の工場で縫製して各国に輸出するわけです。結果、アジア諸国の貿易政策は、いかにグローバルビジネスを取り込めるかを目標に、関税対策というより通商円滑化(たとえば非関税障壁の撤廃、交通網の整備や税関システムの簡素化など)に焦点を置くようになりました。一方、アフリカはほとんどGVCの恩恵を受けておらず、鉱石、原油やコーヒー豆など第一次産品の輸出に頼る比率がむしろ高くなっています。必然的に彼らの貿易政策の焦点は、製造業への移行を助ける新市場の開拓であり、Continental Free Trade Agreement (CFTA)を結んで2017年末までにアフリカ大陸全体を一つの市場にする方向に向かっています。つまり70年代のように「途上国の貿易政策」と一括りにできなくなったわけです。そうした複雑化した国際経済の中で、私どもの経済分析や研究への要望が高まってきているのを強く感じます。

私の仕事はデスクワークだけではありません。UNCTADが実施あるいは参加する技術協力プロジェクトで途上国へ出向き、政府職員やフィールドの皆さんとともに、その国の貿易を「持続可能な開発」につなげる枠組みつくりのお手伝いをしています。GVCへの参加が低賃金で劣悪な労働につながるケースや、生物資源へのアクセスと利益分配に配慮した生産で輸出をのばし、貧困撲滅と環境保持を手に入れたケースのように、貿易は国の「持続可能な開発」に様々な影響を与えます。
今年始まったプロジェクトでは、国際的なエコマークを通じた「環境に優しい貿易促進」の枠組みつくりを支援します。たとえば、南太平洋のバヌアツは質の高いコーヒー、ココナッツ、ココアなどを有機的に栽培していますが、海外に高価で輸出するには、国際的なエコマーク(たとえばFairTradeやIFOAMなど)の保持を求められます。エコマークを持つことによって、環境保全、良い労働環境、公平な利益分配のもとに生産されたと証明できるわけですが、証明のためのプロセスは各生産者にとって安価なものではありません。今年2月の会議では、農業生産者、輸出業者、そして政府機関がエコマークについて話し合える、包括的なシステムの必要性が語られました。エコノミストとして意義のある研究をするためにも、現場の声を直接聞くことは必要不可欠だと思っています。

Q3 国際機関で働こうと思ったきっかけは何ですか。
英国の大学院留学中に、偶然買った日本の新聞で「経済分野のJPO※の募集」の記事を見たことがきっかけです。民間のコンサルティング会社から内定をもらっていたのですが、国際情勢と途上国の経済政策に関わる仕事が面白そうだと思い、応募しました。国連に入ってのち、国連憲章の「We the people of the United Nations..」に続く宣言に深く感銘を受けました。「一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること」のために働けるのは幸せです。
もう一つ、最終的に国際機関で働こうと決めたきっかけは、女性として当時の日本の社会で思い切り働けるのかどうか、確信が持てなかったこともあると思います。実際、国連で働いてきた中で、ジェンダーの差別を受けたことは一度もありません。
(※ JPO ( Junior Professional Officer ): JPO派遣制度は自国の若手職員を国際機関に送り込むために多くの国が実施する制度で、日本では外務省が費用を負担して行っています。詳しくはこちらをご覧下さい。 )

Q4 これまでにどのようなキャリアを歩んで来られましたか。
JPO時代の上司が、国連の正規職員になるには競争試験(現ヤング・プロフェッショナル・プログラム※の前身)が一番の近道と勧めてくれました。JPOの1年目に受験し、合格して今に至ります。
国連で働いて丸10年が経ったころ、「キャリアアップするには経済分析以外の力も身に付ける必要があるかも」と思い、研究休暇制度をつかってハーバード大学ケネディスクールの行政学修士課程で学びました。その「オフ」の1年で、国連システムを外側から客観的に見つめ、同級生たちと、行政、外交、経済政策、人権、の相互作用について語り合えたことが、その後の私の仕事のアプローチに大きな影響を与えてくれたと思います。
(※ 国連事務局ヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP):国連事務局YPPは,国連事務局若手職員を採用するための試験です。詳しくはこちらをご覧下さい。)
Q5 国際機関や所属機関を目指す方へのメッセージをお願いします。
国連を目指す皆様の多くは、人道支援関係に進みたいと思っていらっしゃるのではないでしょうか。経済開発に興味のある方も、UNDPのようなプロジェクト中心の機関を希望されるケースが多いと思います。事実、UNCTADでも日本人JPOをお願いしているのですが、ここ数年は「UNCTADで働きたい」と意思表示してくださる方がいないそうです。
先ほども述べましたが、「貿易と開発」の分野の国連システムのフォーカルポイントとしてのUNCTADの重要性が増してきています。貿易は経済発展のエンジン、そして経済発展は「持続可能な開発」と紛争のない社会を築く土台です。また、UNCTADはWTOや世界銀行、OECDなどへ移っていったり、または移ってきたりという交流が多い職場です。国際エコノミストとしてやっていきたい方々には、とても面白い職場だと思います。
日本人エコノミストの皆さん、ぜひUNCTADへ!
(※UNCTADの職員採用ページはこちらです。)