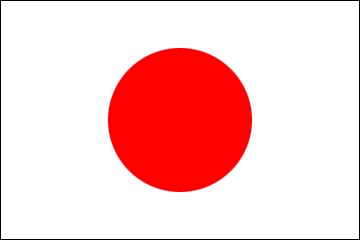ジュネーブの国際機関で活躍する日本人職員(ワシントン条約(CITES)事務局 シニアプログラムオフィサー(知識管理・渉外課長) 大楠 晴子さん)

【ワシントン条約(CITES)事務局 シニアプログラムオフィサー(知識管理・渉外課長) 大楠 晴子さん】
Q1 所属機関の役割や目的について教えて下さい。
トラや、ゾウ、サイなど野生動物の密猟に関するニュースや、フカヒレやウナギの国際取引に関するニュースなどでワシントン条約の名前を耳にした方もいらっしゃるかもしれません。
ワシントン条約は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」と言い、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、野生動植物の保護と持続可能な利用を図ることを目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を、附属書I、II、IIIの分類に区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしており、2017年5月現在で日本を含む183カ国・地域が締約国になっています。
私の所属するワシントン条約事務局は、オーストラリア人の事務局長を筆頭に専門家12、3人と事務アシスタント10人、コンサルタントやプロジェクトスタッフ、インターンが入れ替わりで数人いる比較的小さいオフィスです。

Q2 現在の仕事について教えて下さい。
私は主に事務局主催のプロジェクトの発案、立ち上げや管理、途上国の能力構築(キャパビル)用のツールの作成指揮、事務局内でのドナー支援活動の監督(ドナー支援の交渉や案件作成、支援記録の分析)を任されています。部署内にはソーシャルメディア・広報官、ウェブ・IT情報管理官、それからワシントン条約上の国際取引の電子化・トレーサビリティを専門とする調整官が一人ずつおり、また部署全体で条約内の社会経済関連事項を担当していますので、それらの分野も把握した上で彼らのまとめ役も果たしています。
野生動植物といってもその種類は多岐にわたり、現在3万6千種程が附属書に掲載されています。その中にはごく身近なものから、見たことも聞いたことも無いような種まであり、用途も様々です。私の部署の業務は、これらの様々な分野を広くカバーしており、言わば「なんでも屋」的な立場にあるので、毎日違った課題や挑戦の連続で飽きないのが面白いところです。また、私の専門である自然科学と法律が交差する条約だというところや、キャパビルは途上国のサポートができるという面で最もやりがいを感じます。特に違う専門の同僚たちや締約国の関係者と膝を突き合わせて話し合い、面白いプロジェクトのアイデアが閃いた時はとても嬉しいです。
現在の仕事で大変なのは、条約が複雑な上に小所帯なので各自の担当する仕事量が多いことでしょうか。管理職に昇進して1年が過ぎたところなので、専属で担当する仕事をこなしながら自分のチームの監督もして、事務局全体の戦略的な議論にも関与するということを効率よくやっていくという面ではまだまだ試行錯誤の修行中の身です。
去年10月に3年に一度開催される締約国会議(CoP17)が終わったところですので、現在は今年度の活動計画の始動やドナーからの支援交渉やプロジェクト立ち上げの真っ只中です。如何にドナーの要求や途上国のニーズに応えつつ、執行する身としても興味深いプロジェクトに仕立てて行くかが現在の目標です。
実は長期的な目標はあまり立てず、3-5年毎に自分の成果を見直して新しい計画を練って行動に移す...という感じで運よく今までキャリアを積むことが出来ました。多分数年後には次の挑戦に向けて赴任先を考えることになるかと思いますが、当分は今の仕事をまい進(猪突猛進?)するつもりです。

Q3 国際機関で働こうと思ったきっかけは何ですか。
実は科学者になるつもりでアメリカの大学院で生化学を専攻していたのですが、実験室に籠って研究漬けの生活が性に合わなかったようで...博士号を断念。自分のポテンシャルが発揮できて、なおかつ楽しめる仕事は何だろうと模索していた時に、母の勧めで外務省の。 JPO派遣制度※に応募したのがきっかけです。元々帰国子女で漠然と「国際的な仕事がしたい」というのもありましたし、世界中のどこへでもいいから行って人の役に立ちたいという気持ちも強かったです。
(※ JPO ( Junior Professional Officer ): JPO派遣制度は自国の若手職員を国際機関に送り込むために多くの国が実施する制度で、日本では外務省が費用を負担して行っています。詳しくは。 こちらをご覧下さい。 )
Q4 これまでにどのようなキャリアを歩んで来られましたか。
生化学の修士号を経てJPOとしてナイロビの国連環境計画(UNEP)本部に入り、主に生物多様性関連条約の仕事に携わりました。本部で4年過ごした頃に正規職員のポストをオファーされたのですが、生物多様性の分野でより効果的に仕事をしていくためには法律の知識が必要と考え、一旦国連を離れイギリスの大学院に入り直しました。
法学博士号取得と同時に運良くローマの国連食糧農業機関(FAO)に再就職することが出来、その後UNEPのアジア太平洋地域事務所(バンコク)で生物多様性関連条約担当官として2年半、ワシントン条約事務局(ジュネーブ)にキャパビル調整官として3年間勤務し、2016年から現在のポストに就いています。
国連では一つの機関・国にとどまって専門を極める人と、赴任地を転々として広い経験を積んでいく人に分かれます。私は後者のタイプで、行く先々で培った知識とヒューマン・ネットワークが私の武器だと思っています。
Q5 国際機関や所属機関を目指す方へのメッセージをお願いします。
国連の機関や職種にもよりますが、まず修士レベル以上だということは有利です。それは書面上の学歴というよりも、いかに「自分の専門分野としてアピールできるか」ということが大切だからだと思います。では、博士号がいるのかどうか?これは同僚の間でも話題になるのですが、農業・保健等の分野で高度な専門知識を要する職種では有利かもしれませんが、プログラム調整官としてキャリアを積むに当たっては特に必要はないかもしれません。
私の経験からすると、何らかの専門分野に加えて法律か経済の知識/経歴を合わせ持っていると有利なような気がします。特に開発の仕事をしていると結局その国の法律か経済政策が実際問題レベルで物事を左右しますし、別の機関に転職したい場合での応用性も高いです。
国連機関は日本人職員の需要が多い職場ですが、なかなか「日本人らしさ」(真面目・協力的・謙虚)を生かしつつ「国際的に通用するか」(積極性・戦略性・アピール力)を備えて公募の競争を勝ち取るのが難しいのが現実です。JPO派遣制度やリクルートミッションを利用するなど日本政府に後押しをして貰うのが一番よいと思います。また、当たり前かもしれませんが、日本から離れた途上国に行くほど援助を必要としており、その分仕事も多いので、採用される可能性は高いと思います。若いうちに考えもしなかった異国に住んでみて、開発に携わるのが好きかどうか、国際公務員としてどういう貢献をするのが一番性分に合っているかを体験しておくことは後々きっと役に立つと思います。最後に、何事にも「こうあるべき」と決めつけず、かなり楽観的で柔軟(適当?)でいることも大事です。

(写真はCITESウェブサイトより)
1日の仕事の流れ
8:30 出勤。メールの返信や日程表の確認をしつつ仕事を始めます。太平洋地域にまだ連絡が取れる時刻なので、電話会議をすることもあります。この日は9時から知識管理・渉外課内のスタッフと連絡会議
10:00 様々な仕事遂行のために事務局内で個別に話し合うことの多い時間帯です。
今日は事務のチーフに現在作成中のプロジェクト計画書の予算案等の確認・相談と、事務局長と来月(フィジー)に行く会議やニューヨークで行われる国連海洋会議に関する打ち合わせ
12:00 オフィスで昼食。最近は私の課の空席案内へ送られてきた応募者の履歴書(1つの空席に300人弱の応募がありました)に目を通しながら食べています。実家の母親や日本の友人とSNSで他愛のない話をすることも。
13:30 ヨーロッパやアメリカのドナーと連絡を取るのに一番良い時間です。また、新しい案件が舞い込んだり、事務局内での調整・相談・質問のために皆がオフィス間を走り回ることが多いです。並行作業が多い上、忘れっぽいので保留案件は随時日程表に書き留めておきます。
この日は同僚が準備している書面に文章を提供した後、外部から送られてきたレポートに対して同僚二人と情報共有しながらコメントを入れ、それから野生動物の違法取引関連の活動に支援するドナー調整のウェブ会議に参加。
16:30 オフィスが静かになってくるので、集中力が必要な文書作成に良い時間帯です。18時半ごろ終えて、プールで泳いで帰ることもあれば、インスピレーションが来るのを待ちつつダラダラと夜10時近くまで粘ることもあります。週に1度ぐらいは友人などと飲みに行ったり、外食したり。
この日はやっと現在進行中のプロジェクト計画書の仕上げに取り掛かり、かなり遅くまで粘りましたが終わらず断念して帰宅。