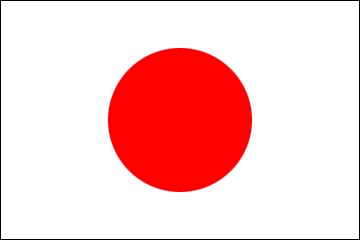ジュネーブの国際機関で活躍する日本人職員 世界貿易機関(WTO)池月 貴子(いけづき・たかこ)さん
令和4年9月30日

現在のお仕事の内容を教えてください。
世界貿易機関(WTO)の貿易政策審査部で統計官として勤務しています。
WTOには、大きく分けて3つの部門があります。1つ目は、貿易に関するルール作りをする部門、2つ目は紛争解決に関する部門、3つ目はWTO協定を円滑に実施するための作業を担当する部門で、私が所属しているのは3つ目の部門です。
具体的には、貿易政策検討(Trade Policy Review:TPR)会合に関連した業務を行っています。TPRは、加盟メンバー(国・地域)が定期的に貿易関連政策の現状を説明し、他のメンバーからの質疑応答を経て、その透明性を確保する仕組みです。メンバーごとに定期的にレビューを受けることになっており、例えば日本、米国、中国、EUは3年ごとにレビューを受けています。レビューは、WTO事務局とレビューの対象メンバーがそれぞれ貿易政策に関する報告書を提出し、その報告書に対して他のメンバーが質問を提出し、その質問に対して2日間の会合の場で対象メンバーが回答する、という流れになっています。私自身は、TPR会合に提出されるWTO事務局からの報告書作成に携わっています。
池月さんは「統計官」ということですが、具体的にどのような業務をされているのですか。
私は、貿易統計の分析という側面から、前述のWTO事務局からの報告書の作成に関与しています。この報告書は大きく分けて、(1)マクロ経済関連、(2)法制度関連、(3)輸出入等貿易政策関連、(4)産業別関連の4つの報告書から構成されており、それぞれの報告書作成に必要な貿易統計のデータを加工・分析するのが私の業務です。各メンバー、OECD、世界銀行、IMF等が作成した公的統計を分析しています。
こうした統計分析に当たっては、どのような専門性が求められるのですか。
まずは、貿易統計・関税に関する専門的知識が求められます。メンバーによって関税の体系は全く異なります。複雑な関税の仕組みを設けているメンバーがある一方で、関税率が5つの種類しかない単純な関税の仕組みのメンバーも存在します。通常の関税率に加えて、FTA、ITA等の協定の関税率、または、関税割当制度の仕組み等の理解が必要ですし、それらの知識をもとに、この場面ではこのレートを用いて計算するといった細かい点まで、関税に関する専門知識がないと分析は難しいです。
関税のデータに加えて、貿易統計(商品・サービス)、外国投資統計、非関税措置に関するデータ、そしてマクロ経済統計の分析ができるスキルも必要不可欠です。私自身は、大学・大学院で経済学を専攻し、貿易関連の研究を行っていたので、こうした分野の専門性が現在でも役に立っています。
あとは、効率的にデータ分析をするために(特に膨大なデータを扱う場合)プログラミングの知識が求められます。私が貿易政策審査部で仕事を始めた時とは違って、様々なプログラミング言語があり、特に若い世代の同僚たちは当たり前のように使っています。私自身も、こういったスキルを習得するために研修を受けたりしました。これからは、こういったデータ分析に使えるプログラミングの知識も必要だと思います。

(WTOのアトリウム)
次に、WTOに入るまでに、どのような経験をされてきたのか教えていただけますか。海外に目を向けるきっかけは何だったのでしょうか。私自身は帰国子女でもなく、高校卒業までは日本で生活していました。
中学生のときに、姉妹都市との交流事業として、市内のいろいろな中学校から選抜された中学生がサンフランシスコで1週間滞在するという機会があり、そのメンバーに選ばれたのが、振り返ってみると一つのきっかけになったのかもしれません。英語の勉強をもっとしたいという気持ちになりましたし、他のいろんな中学校から来た人と話もできたのも大きな刺激になりました。このこともあり、高校から留学したいと両親に伝えたのですが反対され、日本の高校を卒業しました。それでもやはり外国へ行きたいという思いは変わらず、何とか両親を説得して、4年間だけという約束でアメリカの大学に進学することになりました。
アメリカではまず田舎の大学で2年間過ごしたのですが、最初は英語がほとんど話せず、授業についていくのが本当に大変でした。そんな中でどうしていたかというと、まずはあまり英語の必要ない数学とか、音楽の授業を取るようにしていましたね。その後、ワシントンDCの大学に移り、経済学を専攻しました。だいぶ英語は話せるようになっていましたが、膨大な宿題で本当に大変な思いをしました。経済学は数字が使える部分があるので、少しは楽だったと思います(笑)
大学4年生のときに貿易を専門とするコンサルティング会社でインターンをしたこと、また大学の担当教授が貿易と開発を専門としていたことから、現在の仕事である貿易分野への関心が強くなっていきました。ただ、まだその頃は国際機関への就職を意識していたわけではありませんでした。
国際機関の名前がいまのところ一つも出ていませんが(笑)、その後は大学院に進学されたのですよね。
1年間コンサルティング会社で勤務した後、ワシントンDCの大学院に進学しました。アメリカの大学院は一度職を経験してから進学する人が多かったので。
大学院1年目が終わった夏に、UNCTADのインターンをしたのが初めてのジュネーブでした。前述の担当教授がUNCTADのコンサルタントもやっていたという縁で紹介を受けたためです。これが初めての国際機関での勤務経験となりました。
アメリカの大学院生は、インフォーマル・インタビュー(注:OB・OGに、現在の仕事内容を聞いて、自分の職業選択に役立てるというもの)を卒業が近づくと多く行います。私も、法律事務所やコンサルティング会社で働くOB・OGに話を聞きに行きました。その中で、世界銀行で勤務しているOB・OGがおり、その方に貿易関係に興味があるという話をしたところ、「CV(略歴)を送って」と言われて送ったら、世界銀行から面接のオファーがありました。
面接を無事通過し、世界銀行の若手向けの2年間のプログラム(JPA:Junior Professional Associates)で勤務することになりました。そこでは、エコノミストの下で多様なデータのリサーチを経験したのですが、この経験は現在にも生きています。
その後はPh. D に進むつもりだったので、6か月のギャップイヤーで何をしようかと職を探していたところ、たまたまWTOで6か月任期の空席があり、応募して採用されました。当初6か月任期だったのが、任期が複数回更新され、その後は上司の紹介でITCに移り4年ほど勤務しました。ITCの仕事は民間のプロモーションが中心になり、それはそれで面白かったのですが、やはりWTOで再び働きたいと思い、空席に応募し現在に至ります。

(WTOから撮影した朝明けのレマン湖)
WTOで再び働きたい、と感じた、その魅力は何ですか。
ITCだと途上国支援が中心的になりますが、WTOは日本も含めた先進国、アフリカ、中東、ヨーロッパと全世界が対象になるので、全体を見ることができるという面白さがあります。貿易関連政策の調査と分析に関われるというところで、レビュー対象メンバーの専門家と協議できることはとても魅力を感じます。
最後に、これから国際機関で働くことを目指す方にアドバイスをお願いします。
国際機関で働くことを考えている方には、一度インターンを経験することをおすすめします。国際機関での勤務が自分に合うか会わないかを判断する機会にもなりますし、やはり国際機関で働いた経験があるかどうかは、採用に当たって一つのポイントになります。職務経験が同じ年数でも、一度国際機関で働いたことがある人の方が、共通言語・知識を持っているという点で採用のハードルが下がりますからね。
また、国際機関には様々な職種があることを知ってほしいと思います。エコノミスト、弁護士はもちろん、他にも、財務、IT、人事、広報といった幅広い仕事があります。
日本はとても住みやすく、良い国だと思います。ですが、ほんの少しでも海外に興味のある方は、思い切って留学してみることをおすすめします。それによってさらに新しい道が拓け、自分の将来が違ったものになるはずです。
本日はお忙しい中、ありがとうございました。
(2022年8月、インタビュー実施 聞き手:工藤書記官)
外務省国際機関人事センターのホームページでは、国際機関への応募方法、JPO制度など、国際機関に就職するために役立つ情報を多く掲載しています。是非ご覧ください!