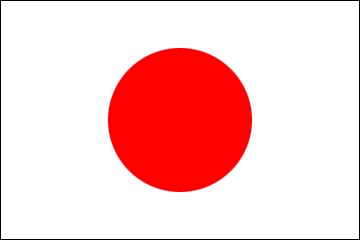インターンシップ報告:千田インターン生
第42回国連人権理事会に約一ヶ月間、在ジュネーブ日本政府代表部のインターンとして参加させて頂きました大学2年生の千田と申します。高校時代、ジュネーブのインターナショナルスクールに通っており、かねてより国際関係の問題に関心がありました。地理や経済、世界情勢の授業において国際的な問題、課題について議論していながら、実際的に国連のようなマクロな機関で、どのようなプロセスやステップによって諸処の問題が解決に向けて取り組まれているのか、と気がかりでいました。将来のキャリアを形成していく上で、そういったマクロな視点について知ることはとても貴重なことだと考え、応募するに至りました。
インターン中の主な仕事内容は、国連欧州本部の ルームXXにて行われる人権理事会にて日本政府の席に座らせていただき、会議の議事録を取ること、会議の進行状況、日本に対する言及の報告でした。さらには、人権理事会と同時進行で行われている非公式会議に出席し、議事録を作成することもありました。
インターンを通じて、事実関係について認識すること、多数決・民主的プロセスの課題、ミクロな視点の重要性について改めて気づかされました。
会議中、議題が代わり、会議が進行しようとも、同じ国同士が大きな一つの問題のもと、様々な人権の問題、人権侵害の観点から違いを非難し合うという場面が多く見られました。その際に、我が国の市民の何千人が被害を受けた、何万人が占領下にあるなど、数的なデータがいくつか出てくることがありますが、互いが互いに違うことを言うので、どこまで内容で信頼できるものかはわかりません。さらには、報告者のレポートのデータを信頼できるものではない、と非難することもありました。そこから、国連を支える第三者の客観的なプロセスによるデータコレクション、事実関係の明確化の重要性を改めて感じ、情報にあふれた現代を生きる一個人として、どの情報を信頼・選択するのかということの難しさについて考えさせられました。
また、会議中様々な国の発言から、何十カ国の国々が我々の声明を支持しているという形の主張を見受けました。その際に、その国々を政治的・領域的・人口的などの様々な観点から、大小について比較・考察することの困難さを感じました。当然、どの国も大小の関係なく取り扱われるべきですが、やはり理事国のような国や、問題において当事者的な立場の国の声明・意見には重みがあります。技術支援や協力が必要な国々がまだまだ多い以上、人権問題について真摯に取り組む上で、各国の外交的な立場が大きく影響してしまう現状に会議の難しさを見受けました。最終的な採択における投票権の有無や席数など、理事国か否かによって持つ権利には所々に差があります。多数決や民主的なプロセスにおいてバランスを取ること、マイノリティをどう見るかの重要性について、会議中に繰り返し出て来た、国内のマイノリティの人権保護の問題と重ねて、マクロとミクロの両側面から考えさせられました。
そして、会議中の先住民族の人権保護に関する議題が印象に残っています。実際に先住民族の方々が会議に出席し、当事者の声を届けたことで、いつもと違う空気が会議場に流れていたように感じました。各国の国益と、ミクロな声とのバランス・均衡を測ることの重要性を認識させられ、国内の事象、特定の民族・宗教、マイノリティに対し他国や国連が介入していくことの難しさも感じました。
約1ヶ月間、右も左もわからない自分をあたたかく受け入れてくださり、また国連人権理事会という、国際問題の解決に向けた実際のテーブルの様子を経験することのできた機会を頂けたことに心より感謝申し上げます。この貴重な経験を、しっかりと自分の将来のキャリア形成に活かして行きたいと思います。本当にありがとうございました。