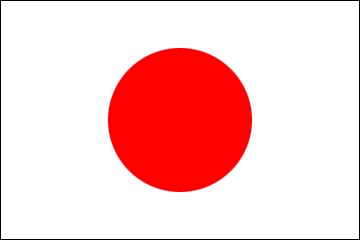インターンシップ報告:八木インターン生
第40回国連人権理事会に1ヶ月間インターンとして参加させていただきました八木と申します。現在はジュネーブにある大学院に在籍しています。以前より人権外交に興味があり、異文化が混ざり合う国際社会において、各国の代表が如何に互いの権利を尊重し合いながら国際問題の解決に取り組まれているのかを実際に拝見させていただける貴重な機会だと思い、本インターンシップに応募するに至りました。
インターンシップ中の主な仕事内容は、メイン会場である国連欧州本部(Palais des Nations)のルームXXに用意された日本の席に日本代表として座らせていただき、本会議の議事録を取るというものでした。会議は毎日朝から夕方までほとんど休憩を挟むことなく行われ、人権班の方々やインターン生の皆さんと協力し、交代しながら議論をフォーローします。会議中は息つく暇もなく次から次へと発言が繰り広げられる様子から、「たくさん議論すべき課題がある中で、寸分の時間も無駄にはしない」といった人権理事会の気概を感じました。
また、「インターン生にも様々な会議の様子を見る機会を」と人権班の方々にお心遣いをいただき、比較的小規模な単位で行われる非公式協議にも何度か参加させていただきました。拷問と虐待に関する議題や、子どもの権利に関する議題など、あるテーマに沿って、特別報告者や国連職員から、市民社会の代表やその分野について研究されている学者など、多岐に渡る方々がそれぞれのケースを用いて様々な角度からその問題についての考察をプレゼンし、議論が行われます。質疑応答などの時間も設けられ、多様な意見を通して解決に向かって議論が進んでいく様子はとても興味深かったです。
他にも印象深かった業務内容として、日本が参加している法の支配コア・グループが主導する共同ステートメントの署名活動があります。日本だけでなく、他国のインターン生とも連携しながら各国代表に声をかけて周り、過去最大の署名数を集める事が出来ました。共同ステートメントの成功のために、少しでも多くの署名を集めなければいけないとのプレッシャーを感じると共に、どの国の代表の方々も気さくに接してくださった事が印象的でした。この署名活動を通して、各国代表の方々とお話できる貴重で特別な機会をいただき心より感謝しています。
本インターンシップにおいて、特別報告者の現地訪問報告書や各国代表の発言を拝聴する中で、現在世界中で起きている様々な人権問題における知識をたくさん得られただけでなく、実際に国連が組織として世界中の人々の人権保護に向けて、どのようなプロセスで政策を進めているのかを直に知ることが出来ました。一概に人権と言えども扱う分野は幅広く、また、日本やジュネーブに居るとあまり身近に感じることのない紛争、拷問と虐待、飢餓、飲み水不足などの極めて深刻な人権侵害問題も数多く取り扱われます。自分の世界情勢に関する知識の乏しさを痛感したと同時に、例えば、人権という概念を利用し暴力の行使を正当化しようとする発言など、私の従来の固定概念に相反する発言を目の当たりにする中で、「なるほど、そういった捉え方もあるのか」と考えさせられる場面も多く、我々の認識では一方的に正しいと思ってしまいがちな事も、他国からしてみれば必ずしも当たり前ではないという点に改めて気付かされました。
また、他にも印象深かったのは、国家による発言以上に、市民社会の発言が多様性に富んでいたことです。特に、現在も国家権力により不当に拘束・収容されている人権保護者やジャーナリストのご家族やご遺族の方々が国際社会に対して、感情を露わにしながら必死に人権侵害状況の理解と向上を求める姿が印象的でした。更に、いろんな国や市民社会の代表が国連人権理事会の政治化を批判している姿も印象的で、人権理事会において改善されるべき点を知ることができた事も大変貴重な経験でした。
また、他国の代表の発言に対して各国代表が拍手をしているか否か、更には他国の発言中に退席するか否かなど、国の代表として会議に参加させていただいている以上は、私たちの行動や言動一つ一つが外交的意味を持つという事を教えていただきました。他国の話をする際はその国名の頭文字一文字を使って表すなど、常に細心の注意を払いながら人権外交に邁進されている人権班の皆様のお姿を通して、日本代表の席に座らせていただく責任の重さを感じ、身の引き締まる思いでした。
人権外交の最前線で活躍されている方々と共にお仕事をさせていただく日々はとても刺激的で、ここでしか出来ない実りある大変貴重な経験だったと感じております。このインターンシップの経験を通して、人権という分野においても一般化して議論することは難しく、国や地域によってそれぞれ違った社会的背景とそれに伴う問題が存在する以上、特定の国や地域の人々の経験に特化した議論が必要とされていることを改めて感じました。今後も「人権」という抽象的な概念やそれにまつわる課題について人類学・社会学的視点からミクロなレベルで研鑽を重ね、少しでも人権外交にお力添えできる人材へと成長していく決意です。1ヶ月間お世話になり、大変にありがとうございました。