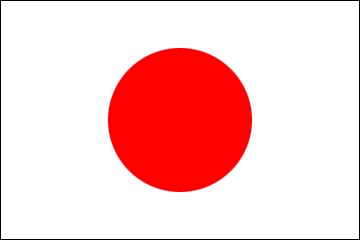館員の声:小笠原インターン生

2019年2月25日から3月22日までの約1か月間、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(以下、代表部)にてインターンシップをさせていただきました小笠原宏輝と申します。現在は北海道大学からの交換留学で、ジュネーブ大学法学部のCTL(Certificate in Transnational Law)というプログラムに在籍しています。私は勉強している国際法が実務ではどのように利用されているのかという点に興味があり、また、外交業務の漠然としたイメージを具体化させたいと考え、本インターンシップに応募させていただきました。以下ではまず、インターンシップの内容について紹介させていただき、次にそこから学んだことを報告させていただこうと思います。
インターンシップの主な内容は、第40回国連人権理事会に出席し、関連業務のお手伝いをするというものでした。具体的には1)本会議への出席・議事録作成,2)非公式協議・サイドイベントの報告書作成,3)共同ステートメントの署名集めの3つです。以下、一つずつ紹介させていただきます。
1.本会議への出席・議事録作成
インターンシップの業務の中で最も中心となったのが、本会議に出席し、議事録を作成するというものでした。国連人権理事会の本会議ではテーマごとに報告や意見交換が行われます。この会議の流れを主に日本語で要約してまとめるという仕事でした。扱っているテーマや各国の立場について、あらかじめ勉強してから会議に出ると非常に面白く、また議事録もうまくまとめることができました。
また、本会議に「出席すること」そのものにも意味がありました。代表部の方が他の業務のため一時的に席を離れなければならない時は、インターン生が必ず日本の席に座っていなければなりません。これは会議において「欠席」が外交上の意味を持つからです。この点は非常に興味深かったです。
その他にも、進行状況や日本への言及を代表部の方へ報告したり、他の国の代表の方やNGO関係者の方がコンタクトしてきたときに対応するのも業務の一環でした。
2.非公式協議・サイドイベントの報告書作成
国連人権理事会では本会議と並行して、別の部屋で非公式協議やサイドイベントが開かれています。その数は非常に多いため、いくつかの協議・イベントにはインターン生が出席し、報告書を提出しました。私はイタリア主催の障がいのある子どものケアに関するサイドイベントに出席し、報告書を作成しました。最前線で問題に取り組むNGOの方の熱いプレゼンテーションがとても印象に残っています。
3. 共同ステートメントの署名集め
日本は法の支配に関する共同ステートメントを実施することになっていました。そのステートメントの支持を署名という形で取り付けるため、共同実施国の代表部の方と連携しながら主にアジア・アフリカ地域の署名集めを行いました。連日多くの国に働きかけた結果、これまでで最多の署名を集めることができました。非常に嬉しかったです。
以上がインターンシップの主な内容です。日々勉強になることばかりでしたが、個人的に印象に残っているのは私が誤って署名シートを持ち帰ってしまったときのことです。これは代表部の方に一言相談すれば防げたミスでした。このとき、なぜ細かな進行状況の報告や相談が大切なのかを実感しました。日本政府代表部という一つのチームにとって、情報や方針の共有は効果的に活動するうえで非常に重要なのです。インターン生であってもそのチームの一員としての責任があることを強く感じ、同時に外交におけるチーム内の連携の重要性を学ぶことができた瞬間でした。
インターンシップ全体を通しては、志望動機でもあった国際法の利用方法と外交の現場についてしっかりと学ぶことができました。国際法に関しては、他国の非難や自国の行為の正当化に多く利用され、日ごろ勉強している国際法の解釈問題がある国家にとっては国際社会の支持を取り付けられるか否かに関わっているということがわかりました。国際社会の評価はその国の信用性に関わり、ひいては実益に関わります。机上の空論のように思える国際法の議論も、国家の代表が必死で合法性を訴えている姿を見ると、学ぶ意義のあるものだと改めて考えました。
また、外交の現場に関しては、日本の代表部の方はもちろん、各国の代表部の方ともお話する機会を得ることができ、また業務の様子も間近で拝見することができました。和やかに談笑する場面もあれば、緊張感をもって真剣に交渉する場面もあり、国家間の関係といえど、外交の現場では「人と人」の関係も重要であると感じました。外交の抽象的なイメージを具体化できたことは私にとって大きな成果です。
最後になりましたが、約1か月間、お忙しいにも関わらず、常に私たちインターン生に気を配り、困ったときには適切にアドバイスをくださった代表部の皆様に心よりお礼申し上げます。この1か月間をこれほどまでに有意義に過ごすことができたのは、間違いなく皆様のお支えがあったからこそです。本当に貴重な機会をいただきありがとうございました。この経験を自身の将来につなげていきたいと思います。