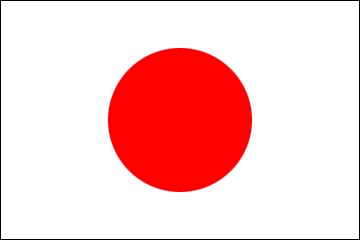館員の声:野間啓佑 インターン生
2018年9月10日から同月28日までの間,在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(以下「代表部」といいます。)でインターンシップをさせていただいた,東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了生の野間啓佑と申します。
私は現在,ビジネスと人権という分野に興味があり,弁護士としてそれを業務の一つとすることができればと考えておりますが,そのために国際機関へ一度は就職して人権に関する生の事実や最新の知識を得たいと思っております。以下では,このようなビジョンをもつ私個人の観点から,今回のインターンシップで得た知見,受けた印象,学んだこと等を報告させていただきます。

1 業務内容
スイス,ジュネーブに所在するパレ・デ・ナシオンにて開催された第39回人権理事会において代表部の業務を補助することが,今回私に与えられた仕事でした。具体的には以下の三つが挙げられます。
(1)最も基本的な業務は,E棟のルームXXにおいて開催されたプレナリー会合で日本政府代表部の席に座り,議事録を作成しつつ議事の進行状況を代表部に報告することでした。議事録は日本語で作成しました。また,他の国家又は団体が日本に関連する事項に言及したときには,その対応の要否や内容について検討するため,その言及があった旨を迅速に代表部へ連絡する必要がありました。
会合中には,各国代表部やNGO関係者が代表部席にコンタクトしてくる場合があり,その対応に当たることも業務の一つでした。さらに,今回日本は「法の支配」についての共同ステートメントを実施することとなっていたため,そのステートメントを支持する各国からの署名集めを行ったりもしました。
(2)非公式会合への出席
妊産婦死亡率決議案やスーダン,ブルンジの人権状況決議案の非公式会合に出席し,その内容を代表部に報告しました。
(3)サイドイベントへの出席
NGOが主催したサイドイベントに出席し,その内容を代表部に報告しました。
2.人権問題の多様性
プレナリー会合では,ジェノサイドやジェンダー平等,先住民の権利,発展の権利等の40を超えるテーマにつき議論がなされました。また,ミャンマーやシリア,南スーダン等の50を超える国々の人権状況も取り扱われました。
私は,大学で国内の人権問題については学修してきましたが,国外の問題を取り扱うことはあまりありませんでした。このため,本会合では世界中で起こっている人権・人道問題について多くの知識を得ることができました。特に,紛争地域では極めて残忍な行為がなされていることや,途上国では水などの衛生環境の整備がまだまだ不十分であることは,日本で暮らしている私にとっては具体的なイメージの湧きにくいものであったため,大変勉強になりました。
また,日本国内における問題についても,先住民の権利に関し(本会合で取り上げられることはなかったのですが),沖縄の人々を先住民と認めるべきであるという見解があることを新たに知りました。また,有害廃棄物についての議論では,複数のNGOや報告者から福島原発の問題について具体的な言及がなされ,国際的にも未だ関心の強い問題であるということが確認できました。
私は,今回のインターンシップを開始するにあたり,事前に日本の新聞のみならずBBC等により人権問題に関する知識を取り入れてはいましたが,本会合に参加してそれはまだまだ不十分であったことを痛感しました。しかし,議論についていったり各国のステートメントの意図をくみ取ったりするためには,テーマとなっているそれぞれの人権問題について前提となる知識がなければならないと思います。私の業務の中心であった議事録作成の際にも,あらかじめテーマとなっている人権問題についての知識を得ておけば,ステートメントの内容を正確に理解したり重要な部分をうまく切り取ることができたりしたため,よりよい議事録を作ることができました。そのため,日頃からより積極的に国際的な問題にも目を向けておく必要があると感じました。加えて,被占領パレスチナ地域等の問題に関しては,その歴史についても議論を理解するための前提知識となるため,そのような知識についても得ておかなければならないと感じました。
3.語学の必要性
理事会の会合は6か国の国連公用語に同時通訳されていたため,私は英語を聞き取りつつ日本語で議事録を作成していました。もっとも,会合では多くのテクニカルタームや普段は使用されない動詞等が多用されることに加え,各国の英語にそれぞれのクセがあるため,最初のうちは英語の聞き取り自体に困難を感じていました。もっとも,毎日大量の聞き取りをしていたことや議論の前提となる知識を得てから会合に臨むようにしたことから,徐々に慣れていき,ステートメント等の内容を正確に理解することができるようになっていきました。
また,今回私は複数のレセプションに参加する機会があり,そこで多くの他国のインターンと交流を深めることができました。そこで驚いたのは,他国(特にヨーロッパ)のインターンの中には,母国語と英語に加えて他の国連公用語を話せる人も多くいたということです。
日本人が国際機関において働く場合に最も大きな障壁となるのは語学であるといわれますが,今回のインターンシップではそのことを,身をもって痛感しました。今後,海外で学位を取得すること等により専門性・語学ともに伸ばす機会をぜひ作りたいと思いました。