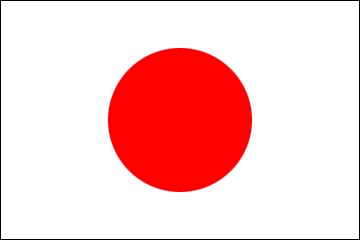インターンシップ報告:土井インターン生
2019年6月24日から7月12日の3週間、第41回国連人権理事会のインターンシップをさせていただきました、大学4年生の土井と申します。私は2018年9月より約1年間ジュネーブ大学に交換留学しており、当インターンシップは、世界各国が抱える人権問題を改善するための外交の現場を直接体験できる機会であると同時に、将来紛争解決・平和構築といった国際協力分野で働きたいと考える自身にとっても重要な経験となると考え、応募させて頂きました。
期間中の主な仕事内容は、国連欧州本部のルームXXで行われるプレナリー(本会議)に日本政府代表として出席し、議事録をとることでした。また、会議の進行状況や日本に関する言及があった際の随時報告、期間中に並行して行われる非公式協議やサイドイベントへの出席と議事録作成、他国の代表部やNGO関係者との仲介などの業務も行いました。
プレナリーはミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官による世界の人権問題の状況の報告から始まり、性的志向やジェンダーアイデンティティー、女性に対する差別や暴力、表現の自由、移民や国内避難民(IDP)の権利、ビジネスと人権、気候変動、貧困、教育といった実に様々なテーマや、いまだ内戦が続くシリアやロヒンギャ問題に揺れるミャンマー、難民問題や不安定な政情を抱えるベネズエラ、スーダン、コンゴ民主共和国など特定の国における人権問題などに関する議論が毎日朝から夜まで行われました。非公式協議では、中心となる国々が作成した決議の案文に対し、各国が様々な提案や意見を述べながら、その内容や文言をどうすべきか話し合い、まとめていました。私は子供の強制結婚や、コンゴ民主共和国のカサイ地区に関する協議に、代表部の方と共に出席させていただきました。また、国際機関内でのジェンダー平等の推進などに関するサイドイベントに出席し、報告書を作成しました。
これらの業務を通し、改めて人権問題の切り口の多さに驚くとともに、日々扱われているテーマに関して、各地の現状や課題、解決に向けた取り組みを学ぶことができました。大学で国際関係や国際協力を学んでいても、例えばアゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノ・カラバフ自治州をめぐる紛争など、これまで全く知らなかった国際問題や人権問題もあり、発言の内容や仕方などから、各国の外交の姿勢もうかがい知ることができました。最後の2日間で行われた決議の採択では、各決議の担当国をはじめ、様々な国が自国の最終的な立場やその理由を表明しつつ投票が行われ、特に論争の多かった決議が採択されたときには議場で拍手が巻き起こり、皆で喜び合う様子が印象的でした。これらの決議に基づいた政策が今後各国で実施されると思うと、その重みや、世界中の国が議論し一定のコンセンサスをつくることの重要性を感じました。
また、日々の議論における特別報告者や各国、NGOのステートメントから、現地で人々がいかに苦しんでいるのかが伝わってきて胸が痛かったです。私たちは日頃、そういった世界で起きている問題をただの問題・ケースとして他人事にとらえてしまいがちですが、当事者の苦しみや悲しみを自分ごととして捉え、一刻も早く問題を解決するにはどうすべきかを考えて学び、行動することが、とりわけ自身のように国際協力を学ぶ者には必要なのだということを実感しました。
一方で、自国への様々な非難や勧告を内政干渉であるとして受け入れない国が少なくなかったり、特に上記のナゴルノ・カラバフをめぐる紛争のような2国間(あるいは数か国間)の問題では、議論が平行線をたどることも多く、どうにか解決に向けて一歩踏み出すことはできないのだろうかとフラストレーションがたまることもありました。そういった国同士の問題は、やはり最終的にはその国同士で解決するしかないのであり、理事会でなされる決議や勧告もその実行は各国にかかっている以上、理事会による実際の問題解決には限界があることを感じました。さらに、各国やNGOを中心に、理事会自体の政治化や議論の仕方を批判する声もあり、国連会議の現実的な課題も知ることができました。これまでぼんやりしていた外交、国連会議のイメージが明確になり、その理想と現実の双方を学ぶことができたのは大きな成果です。
日本政府代表部の一員として、人権理事会という外交の現場を直接見て関わることができ、ジュネーブでしかできない貴重な機会を頂けたことに感謝の思いでいっぱいです。当インターンシップは自身の研究にはもちろん、今後の進路を考えるうえでも非常に重要な経験になりました。この経験を必ず将来に活かし、現場で苦しむ人々の人権を守り、世界の平和に少しでも貢献できる人材になってまいります。