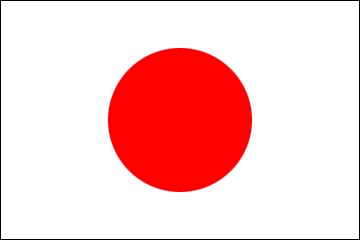館員の声: 石立郁美 インターン生
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の政務・社会部(人権班)で、2016年6月から7月にかけてインターンをさせていただきました石立郁美です。現在は、ジュネーブにある国際開発研究大学院(IHEID)の国際問題学修士課程に在籍しています。インターン中は、第32回国連人権理事会に日本政府代表団のインターン生として参加させていただきました。今回は、このような形でインターンシップの感想を書かせていただく機会をいただきましたので、インターン生の視点から人権理事会やインターンの内容について紹介させていただきたいと思います。
国連人権理事会とは
人権理事会は、人権と基本的自由の促進と擁護に責任を持つ国連の主要な政府機関であり、総会によって選出された47か国の理事国によって構成されます。この人権理事会は国連欧州本部で開催され、本会議は天井が特徴的なRoom XXという部屋で行われています。議場では、理事国を中心とし、その周りを非理事国が囲む形になっています。今回、日本は非理事国としての参加でした。天井はもちろんですが、議場に入りまず驚いたことが、NGOに対しても各国と同様に席が設けられていることでした。会議中も国家と同様に、NGOが議題について発言する機会も設けられており、国家とは別の視点からの発言が多くみられました。国家によって代表されない声もNGOを通して国際社会に届けようという人権理事会の仕組みが、大変興味深かったです。また、本会議とは別に個別交渉が各会議室で行われており、一つ一つの文言に対して各国が交渉を行っていました。

【Room XXの様子】
インターンシップの内容
インターンシップの主な内容は、本会議の議事録を取る事でした。議事録を取るというのは単純な作業のように感じていたのですが、英語で進行する会議を同時に日本語に訳して議事録を取らなければならず、とても難しかったです。どうしたものかと考えていた時に、担当していただいた代表部の方の議事録を見せていただきました。そこには、各国間の意見の相違や交渉の流れなどが簡潔にまとめられていました。その際に、「せっかくの機会だから、自分の勉強だと思って人権理事会に参加してみたら」とアドバイスをいただきました。
それまでは議事内容をただ聞き取って書くことに必死で、あまり内容を理解していなかったと反省しました。そのため、初めて聞いた言葉や事例についてメモをして、寮に帰ってから友人に聞いてみたり、インターネットで調べてみたりといった工夫をしてみました。また、別の会議室で行われている個別交渉を見せていただく機会もいただき、会期の終盤には議題の背景がだんだん理解できるようになり、各国の発言の背景や国家間のつながりも少しずつ見えてきて、大変面白かったです。
インターンシップを通して、特に印象に残っているのが、6月30日の人権理事会において “Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity” に関する決議が採択された場面です。採択に当たり、多くの修正案が提出されたため、各文言に対して繰り返し投票が行われました、3時間半に及ぶ投票は人権理事会の歴史の中でも最も長い時間が費やされたとのことでした。会場はもちろん、観覧席にも多くの人が詰めかけていました。最終的に、修正された決議の採択が可決されると会場に大きな拍手が起こり、抱き合って喜ぶ人もいました。人権理事会において各国の発言は一国を代表しているため、一人一人の国民に焦点があてられることは少なく、しばしば人間味のない議論ではないかと感じてしまう事がありました。しかし、この決議の採択を通して、その決議を待っている人がいる事を感じることができ、大変貴重な経験となりました。

【決議採択時の様子 (UN Web TV より)】
おわりに
人権理事会では、3週間という短い期間でしたが多くの事を学ばせていただくことが出来ました。この経験を今後の大学院での研究や進路の決定にも活かしていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

【筆者・石立郁美】