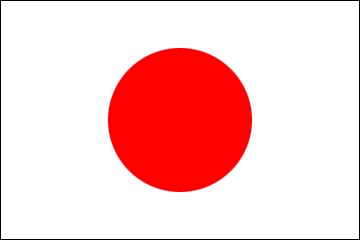インターンシップ報告:浦野インターン生
2019年2月から3月にかけ行われた第40回国連人権理事会会合に、在ジュネーブ日本政府代表部人権班のインターン生として参加させて頂きました、浦野と申します。現在、ジュネーブにある高等研究所の国際法修士課程に在籍しており、国際人権法、移民・難民法、強制移住を専門としています。今回は、様々な人権課題の解決に向け外交面ではどのような意思決定がなされているのか、またNGOなどのオブザーバーの国際会議における役割や立ち位置を観察できるよい機会と考え応募しました。インターン生の主な業務内容は、議場(Room XX)での本会議に出席し議論のメモを取ること、各国代表部・NGOとのリエゾンの補助、必要に応じ各国・NGO主催のサイド・イベントに出席すること、共同ステートメントへの他国からの署名集めなどでした。以下、業務を行う中で印象に残った主な3点をまとめます。
1. 時勢に即した議論
約1ヶ月間の会期を通し、議論は常に国際社会が対面している人権に関する懸念や変わりゆく状況を反映していました。昨今不安定な内政状況が懸念されている某国がハイレベルセグメントにてステートメントを行う際には、現政権を認めないとする国々が退場し議場に緊張が走りました。またある加盟国が宗教的過激思想によるテロ攻撃に見舞われた日に折しも「ナショナリズムと過激主義」に関する一般討論があり、発言者は各々の言葉で事件の背景に触れながら主張していました。そのため会期が始まってからは議論にもれなくついていくため、最新のニュースを常にチェックするようにしていました。
2. 意思決定への慎重さ
人権理事会は2006年に国連総会決議により創設された機関で、今回の会合が40回目ということからわかるようにまだその歴史は浅いといえます。理事会は毎年3回行われる会合のそれぞれで決議案を採択しますが、その文言に法的な拘束力は発生しません。しかしながら日本が今回参加した法の支配の促進に関する共同ステートメントへの署名集めの場では、ある文言の意味するところについて署名の前に説明と確認を求める国が存在するなど、法的拘束力の有無にかかわらず、一つ一つの言葉の指す概念への理解を怠らず意思決定を行う外交の側面を垣間見ることができました。
3. 人権とは何なのか?
約1ヶ月間の会議を通して感じたことですが、マルチ外交というのは良くも悪くも時間のかかるプロセスです。様々なテーマの討論(dialogue)が行われましたが、議題そのものに関する白熱した議論というよりは国々の公開の場での外交の場、といった印象を持ちました。各国・オブザーバーは要望・抗議などが織り交ぜられたステートメントを発することで、それぞれのプレゼンス・立場をその都度明確にしていたように思います。また会期の終盤には決議案の採択が行われ、最後のコメントの中で人権問題が政治化(politicization)やダブルスタンダード、内政干渉の道具となっているとして懸念を示す国々が存在しました。国際法そのものもそうですが、「人権」が法概念として未成熟であることを感じる場面でした。また今回の会議に参加させていただくまでは、NGOの役割は市民社会を代表し国際社会へと彼らの声を届けることと考えていましたが、必ずしもそうではなく、議題に関係のない場合でもそれぞれの主張を声高に主張する政治・圧力団体としての顔を見ることもあったように思います。
終わりに
約1ヶ月と短い間ではありましたが、普段の学生生活では入る機会のない国連欧州本部にて勤務したこと、外交の現場における議論を見ることができたことは得がたい経験でした。また人権班の皆様、インターン生の皆さんに支えられ共に勤務できたことはとても光栄なことでした。貴重な機会を頂いたことに感謝しております。